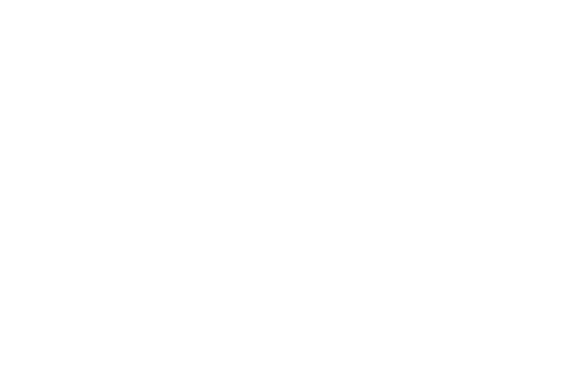二口 大学 役者
芝居を始めて十二年になる。この年月は長いのか短いのか僕にはわからない。相変わらず漂流しているなあ、と思う。様々な問題意識によって生まれてくる不安、孤独、疑心暗鬼等、漠然とした塊がいつも隣りであぐらをかいて居座っている。だからといって悲観しているわけではない。結局はおめでたいやつなのだ。大真面目に不真面目をやっているのんき者なのだと考えている。
舞台はひとつの通路である。作品によって流れるものが異なり、質・量が違う。それだけだ。何を通過させるか、作者の意図によって決定される。そして実演するものの手で具現化される。観客は「見る」行為によって実は「見られる」存在になる。通路は舞台から客席へそして人々の生活へとつながっていき、また舞台に帰ってくるという筋道をたどる。舞台自身が独立し他との関係を持たないものなどどこにもない。常に流れは双方向なのだ。不定形で流動的、俳優とはこの通路の激流に身を置く者のことだ。様々なものを通過させる身体性、「通過体」として存在しようという意志を持ち続ける者。そして、それが僕の仕事なのだと思っている。
昨年夏、西陣ファクトリーGardenというところで「本を読む」という試みをさせていただいた。声を掛けてきてくれたのは照明家の岩村原太さん。氏が呼び掛け人となる、麒麟同盟週間の第五週目にあたる作品、米倉斉加年作「多毛留」。僕はそこで文字通り本を読んだ。かつてのネクタイ織りの工場跡で、俳優が身体表現として実際に本を片手に読む。ただそれだけの行為。しかし、豊かな舞台だと思った。説明的なものは一切ないが確実に人がそこに生きている。過剰でおしつけがましいドラマが多い中で、これはやるべき仕事だと思った。当時、いち俳優として向かうべき方向性を見失っていた僕にとって、今がどういう状態なのか何が足りず何が邪魔をしているのかを確かめるための舞台だったのかもしれない。
百行にも満たない文字を女優と二人、日本語とハングルを使って読み分ける。約四十五分間の作品。稽古は、こうしなければならない、こんなスタイルで、という要求は全くないところで行なわれる。書かれてある言葉を表現するのではなく、いち文字いち音の間に感じ取れる感覚をどう確実に体験するのか。内なる声にじっと耳を澄ませ、作者の息づかいを肌で感じることに集中する。行為を積み重ねるのではなく、経験として身についている不要なものを削ぎ落としていく作業。きつい行程。色々なものがこんなにも身にまとわりついているのかとはじめて知った。
乱暴な言い方をすれば、削ぎ落としていく過程の中で、僕は俳優ではなく、ひとりの夫であり父親であり息子であることに気付いた。生活者としてのひとりの男であると。作品はそのひとりの男の中を激しく通過していく。そして僕という通路は僕だけのものではなく、息子ともそして顔知らぬ誰かとも深い井戸の底で脈々とつながっている。掘進夫のごとく、作業しつづける行為こそが、僕にとっての演劇と生活者を結びつけることだったようだ。今僕は「本を読む」を通して、さまよいながら2000年を迎えようとしている。