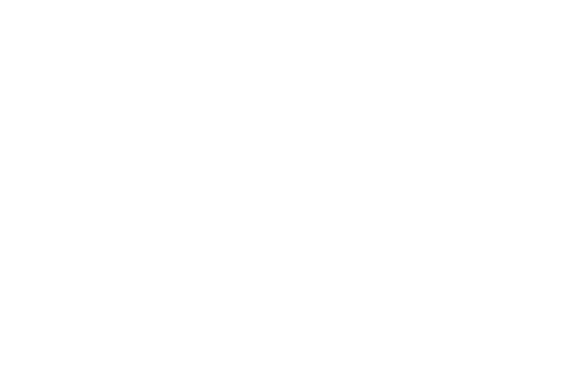田辺 剛 劇作家・演出家
戯曲(演劇の脚本)を書き始めて三作目のものが、日本劇作家協会というところが主催する戯曲賞の最終候補になった。この戯曲賞では最終候補に残るとそれぞれの候補作が一冊の本にまとめられて出版されたり記念品をもらえたりする。自分の書いたモノが活字になり本屋に並ぶということはなんだか大げさな気もしたが、それでもやはり嬉しかったし、知らせを受けたときは小躍りしてしまった。
最終候補六作の中から受賞作を選ぶ最終選考会は、この戯曲賞では公開で行われる。2001年12月、東京・新宿の紀伊國屋ホールだった。審査員が壇上のテーブルについて議論を始める。わたしもその客席にいた。結果はわたしではなく、というよりわたしの作品はほとんど話題にものぼらなかった。わたしの作品を最終候補に推した審査員にはその席上で「後になって読み返すとどうしてこの作品を推したのか自分でも分からない」とまで言われる始末。なんじゃそりゃと脱力して、座席からずり落ちそうになった。
それでもこの出来事はわたしの意識を変えてくれた。その時の審査員は、別役実、清水邦夫、斎藤憐、小松幹生、永井愛、鴻上尚史、横内謙介の各氏。司会は松田正隆さん。少なくともこれだけの先輩方がわたしの作品を読んでくれたという事実。選考会に出席して初めて実感した。そう、わたしの創作は知らず知らずのうちに京都という狭い街の中で、内輪向けの活動になっていたのだ。井の中の蛙とはまさにこのこと。そして自問自答を繰り返した。自分の表現がどれだけの人々に通用する力を持っているのか、あるいは特定の人であってもいい、一人の観客あるいは読者をどれだけ惹きつける力を持っているのか。そして、そんな力を養うためにはなにが必要なのか。
この選考会の後、わたしは大学院を中途退学した。戯曲を書くということを徹底してやってみたいと思ったからだった。当時25歳。とりあえずの期限を30歳までとして、そう親と約束をして、それまでになんらかの展望を見いだせなければはっきりやめると宣言してひたすらやってきた。幸いなことに、30歳ギリギリで続けていくための足がかりのようなものは見つけられた。それはとても不確かで危ういものだけれども、わたしは演劇を続けるということをちょうど決断したところだ。今度はもう期限はない。来月までかもしれないし、5年後あるいは30年後かもしれない。実生活が行き詰まればそれで終わりだ。
この先どうなるかは分からないから、あの分岐点、すなわちあの最終選考会の後で初めてしたわたしの覚悟が正しいのか間違っていたのかはまだ分からない。
それでもとにかく根拠のない自信と楽観論で行けるところまで行ってみようと思う。
Page Top