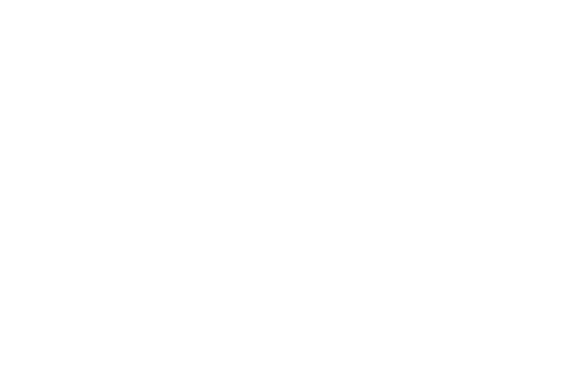清水 忠文 舞台監督
大学を卒業してから十年が過ぎた。学生演劇にかかわっていた僕にとって大学の卒業時が一つの分岐点であった様に思う。十年前は、まだバブルの時代で就職に関しては売手市場で内定を四つも取ったという友人も少なくなかった。
僕自身はと言えば芝居を続けていくのか就職をするのか随分と迷っていた。芝居を続けて行くということは、アルバイトで生活しせいぜい年二回程度の公演をするという事で、行く末何の保障もない。一方、就職すれば朝から晩まで仕事、休日も返上して仕事。自分の時間など持てるはずもなく、まして芝居など出来るわけがない。ただし仕事をしただけの給料はしっかりともらえる。入社した年の冬のボーナスが百万円などという話も特別にめずらしい事ではなかった。
心配性で極く小心な僕の性格からすると、卒業したら就職をするというのが当然で、それ以外の選択をするとは考えてもみなかった。芝居をするという選択肢が物理的にはあるとわかっていても、それが僕の中でなかなか現実味を帯びてこなかった。ただ、バブル時代特有の「金」第一主義的な風潮に対して漠然とした懐疑があったのと、栄養ドリンク片手にバリバリと仕事をこなすサラリーマンの自分を想像する事がどうしても出来なかった。
そのうちにプライベートで失恋という学生時代にはきっと誰でも一度は経験する事態に遭遇して、がっくりと無気力になってしまった。もともとあまり免疫もなかったものだから、この無気力はとても長引いた。物事をいろいろ考えたり決断したりするのが億劫で何もしたくない状態が続いた。
そんな時観た芝居が「蝶のやうな私の郷愁」だった。さほど期待して観に行ったわけでなく、つき合いの義理と時間つぶしみたいな気楽な気持ちで観たのだが、これが琴線に触れた。一時間未満の短い二人芝居だったが涙が、びっくりする程出てきた。もしかしたら芝居を観て泣いた初めての経験だったかもしれない。この芝居を創っていた先輩に声を掛けられた事もあり、あっさり芝居をやっていく事に決めた。
この十年、いろいろな事があったけど今でも芝居とかかわり続けている。経済的に苦しい生活を強いられているし、先々に何の保障もないのは十年前と同じである。まあそれは今のところ仕方がないとも思うが、もっともっと頑張らなければいけないとは思っている。