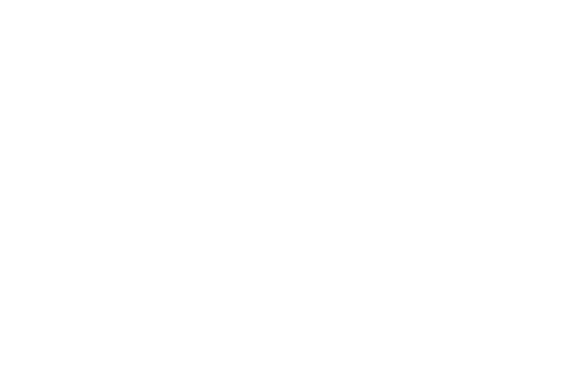丸井 重樹 ベトナムからの笑い声代表/C.T.T.事務局
去年の大晦日。五年ぶりに家族揃って年を越した。
うちは野球一家だ。父親は高校時代、春・夏甲子園に出場、国体にも出た。しかもセカンドでキャプテン。真ん中の弟は、父親の才能を受け継ぎ、やはり春・夏甲子園に出場。全日本選抜のメンバーにも選ばれ、オーストラリアに遠征。あの福留(現・中日)とサードのポジションを争った。現在も駒大で野球を続けている。一番下の弟も、もちろん野球少年だ。
僕は、高校に進学すると同時に野球と縁を切った。父親の「野球遺伝子」は、長男に受け継がれなかったと悟ったからだ。野球と縁を切るからには、他の運動部に入るわけにはいかない。そう思って、最初に訪れた文化部。そこがその後の人生を決めるとは思いもよらなかった。
大晦日はすき焼だった。五年ぶりの一家団欒は、予想通りそれほど盛り上がることなく、静かに年が変わろうとしていた。めったに顔を合わさない家族が、用事がなければ電話もしない兄弟が、大晦日に揃って鍋を突ついたからといって、会話が弾むわけはないのだ。
あれは、紅白歌合戦の勝敗が決まろうとしている頃だった。「実は俺、芝居を仕事にしようと思ってるんだけど」
演劇はエンターテイメントだ。巷で流行の「関係性の演劇」も、ハートフルコメディも、アングラも、観客に面白いものを観てもらおうというサービスだと思う。この不況の中、経済をまわしていくのはもう「モノ」じゃない。情報、流通、エンターテイメント、そういう「形のないモノ」が経済をまわしていくんだろう。大学を卒業するにあたって就職を考えた時、そんなことをぼんやりと思った。というのは、こじつけに過ぎない。
コミュニケーション不足の時代らしい。情報化時代なのに。様々なコミュニケーションツールが溢れているのに。「間接的でヴァーチャル」なコミュニケーションが流行っていて、それはとても便利でお手軽だ。演劇には、「生でリアル」なコミュニケーションがとっても必要。演出家と俳優、俳優と俳優、そして俳優と観客。それぞれの距離と人間関係。時間はかかるし、微妙だし、面倒くさい。しかし、このコミュニケーション不足の時代だからこそ、「生でリアル」なコミュニケーションが織り成す“芝居”が求められている。だからこそ演劇には可能性がある。というのは、僕の予想に過ぎない。
「あんたの好きにしたらええがな」と母親は言った。
「自分がええと思ってたらそれでええから」と父親も言った。
家族には内緒で芝居を続けていた。野球一家だったし、父親も母親も常識人だ。ましてや僕は長男だった。とてもじゃないが、「芝居で食っていく」なんて告白できない。決心がついて一年半。五年ぶりに家族が揃う正月。ずいぶんと酒の力も借りて、意を決しての告白に対して、両親は意外と冷静だった。大人だった。そして後押しされた。後ろ盾ができた。これで何の気兼ねもなく自分の進路を進むことができる。というのも、ただの気休めにすぎない。
演劇の魅力とか、演劇の果たす社会的役割とか、自分は会社員に向かないからとか、目立ちたがりだからとか、一緒に芝居を創ろうと言ってくれる仲間がいるからとか、まだまだやりたいことがあるからとか。みんなみんな、僕が演劇をいまだに続けていて、これからも一生関わっていこうとする動機足りえない。
きっと成り行きなんだろうと思うのだ。しかし、全く自分の意志がなかったわけではない。絶対にこうしなければならなかったというわけではなかった。でも、高校一年生の春、演劇部のドアを叩いた瞬間から続いてきた、「成り行き」。僕はそれで満足しているし、後悔はしていない。どころか、あの時、あの部室のドアを叩いてよかったとさえ思っている。その後の「成り行き」で出会った全ての人に対して、感謝しきれないほど感謝したい。全ては「成り行き」だった。と思う。これからもきっとそうだろう。
僕は、特別自分に演劇的才能があるとは思っていない。しかし、「才能とは夢を見続ける力のことですよ」と鴻上尚史(第三舞台)は言った。「現状維持は後退である」と、重政隆文(劇評家)も言った。拒むことだってできた「成り行き」だった。しかし僕は続けてきた。続けられた。この先も、さらに前に進もうとしている。「成り行き」に身を任せて。…って、これもただ意地はってるだけだったりして。
Page Top