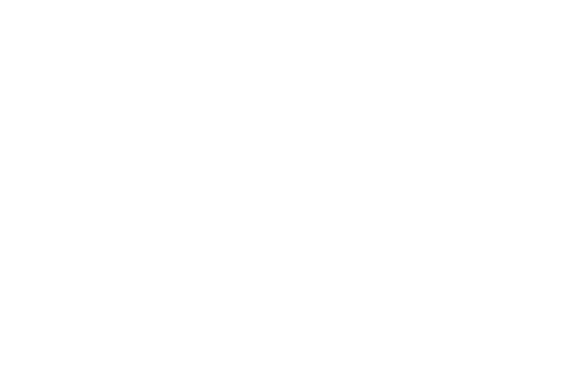あごう さとし 劇作家・演出家(執筆当時WANDERING PARTY)
「え? 今日はハンドン?」
正午、突然家に帰って来た息子に母親はすっとんきょうな声を出した。
「いや、会社やめてきた」
「・・・まあ、とりあえず着替えて来たら。焼き飯ぐらいしかないで」
笑っていいともを観ながら昼食をとって、とりあえず劇団をやるから京都にいくと言葉少な
く伝えた。「ええ? そうなん。」母親は、あまりに急な事だったせいか、思ったよりリアクシ ョンは薄かった。言う事は言ったぜと思い、昼寝した。
僕が劇団で戯曲らしきものを書くようになったのは、劇団の第3回公演からです。
劇団には当初、作・演出が他にいたのです。そもそも、僕たちはその人の作品を上演する
ために集まったのです。こういうことを書くのは、自分以外の人の事にも触れてしまう ので気が進まなかったのですが、書く事にしました。
旗揚げ公演は、若い力があふれ華やかで力強いものになるはずでした。軽薄で人の良い僕らは、輝ける未来を疑わず、旗揚げ公演は必ずや素晴らしいものになると信じてい ました。しかし、現実はそうではなかった。演出家は稽古に来ず、現れたのは本番の3 日前。そこではじめて台本の前半部分が提示されました。残り半分は、本番の前日にあがりました。男5人がほぼ出ずっぱりの2時間のお芝居でした。その数日間は、まともな睡眠もとれず、疲労と緊張の極致といった状態でしたが、誰一人諦める者はおりませんでした。何か得体の知れないものに飲み込まれてしまいそうになるのを、必死で抵抗していたのです。誰もその状態を嘆かず、人を責めず、馬鹿話しでゲラゲラ笑いながらも、体力の続く限り、稽古と準備に励みました。有り難かったのは、そんな酷い現場に、当時つきあってくれたスタッフさんも不満一つもらさず、献身的に協力してくれたこと です。
迎えた本番は、いつ止まってしまうかも知れぬ状態の中、最後までたどり着く事 ができました。ただ、伝えようとしても伝えようとしても、客席の闇に全てがかき消さ れていくような、ここでもまた得体の知れぬものに飲み込まれてしまいそうな、絶望的な感覚が僕らを支配していました。その公演が終わった時、作・演出の男はそれまでには聞いた事のない丁寧な言葉遣いと振る舞いで、僕らに謝罪してまわりました。そして、何も話さなくなりました。
いつものように接することは、その時から出来なくなってしまいました。
次の公演でも、演出家は稽古に来ず、本番2週間前になっても台本は一枚も出ません
でした。その夜、僕たちは彼を呼び出し京都大学のA号館に集まりました。
「書けるか?」と問いかけたところ「わからない」と彼は答えました。それから長い沈 黙が続きました。10時頃に集まって、気づけば夜中の3時になっていました。僕らはただ黙って座っていました。金本は居眠りをしていました。そうして、今の代表の高杉が「もうやめていいで」と一言いってその場をさりました。この瞬間、僕らは劇団の核心を失う事になりまし
た。残った彼と僕と金本はさらに一時間、ただ黙って座っていました。何か彼に言いたかったのだけれども、言葉がうまく出てきませんでした。彼と僕は高校からの付き合いで、
彼は、一つ先輩でした。 演劇というものを体当たりで僕に刷り込んだ最初で唯一の人でした。僕は、この人ほど愉快な男はいないと思っていました し、この人となら、一緒に人生かけてやってもいいと思い、勤めた会社をやめて劇団の 設立にかかわりました。それが、よもやこういう事態になるとは思いもよらなかったのです。彼の台本が遅い事は分かっていましたし、繊細な部分も含めて引き受けられると思っていたのです。悲しみとも怒りとも無力感ともとれぬ複雑な気持ちになりました。
最後に教室を出る時に、僕は彼に何かを言ったはずですが、何を言ったのか、今は覚えていません。ただ、彼の寂しそうな申し訳なさそうな笑顔だけが脳裏に残っています。僕が戯曲を書く事になったのはそれからです。「劇団の作・演出がいなくなっても劇 団は潰れない」という意地が、戯曲を書く決定的なモチベーションになりました。僕に とって戯曲を書くという事は、失った劇団の核心を創るということでした。あの得体の知れない闇に飲み込まれないようにするためのものでした。