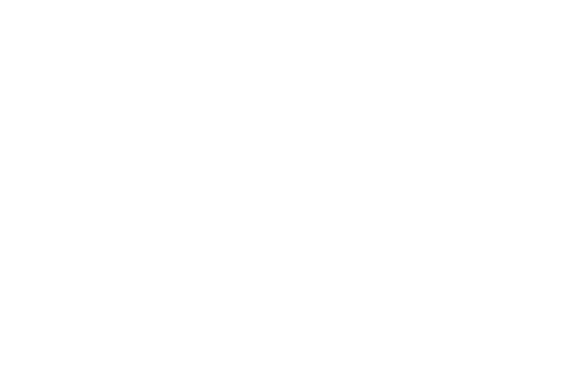鈴江 俊郎 劇作家・演出家・役者(劇団八時半)
初めて台本を書く気分ってどんなのだったろう。……目に浮かぶのは図書館の風景。大学の図書館だ。
当時私は一年留年中。クラスの同級生はほぼ全員卒業してしまっていて、友達はもはや劇団にしかいなかった。その劇団の友達もほぼ失いかけていた。私を含む創立メンバー四人はそろいもそろって留年していたが、青山という男以外の三人は今年こそは卒業・就職しようとしていた。座長だった私も就職組。いまやOBだ。運営の中心はその青山に移っていた。しかしこいつがひどい。それまでは曲がりなりにも規律ある劇団だったのに、あらゆる仕事の〆切は守らない、追い詰められると稽古はすっぽかす、劇団員の女の子の過半数に手を出す、しかもその当の女の子たちは誰もそれに気づかないで円満にやっている。だけどわれらOB三人は嫉妬に駆られた卑劣な告げ口野郎だと思われるのがいやで教えてあげられず。おかしなプライドに捕らわれていた。しかし正義感は(実は嫉妬心は)彼女達の身を案じれば(くやしくてたまらんので)告げよ告げよとせっつくし、とても苦しい心境に追い詰められていた(ほんとにうらやましかった)。 さらにそのいけない女の子のうち一人は別の劇団員と公認の交際中だったし、もう一つ言うと青山は別の女子大生と白いマンションで同棲していた。こちらは一部非公認。もう複雑でわけわからない。われら三人はあきれつつ、時々青山を問い詰める。青山は謝る。誠心誠意。とても感じのいい奴だ。許したくなる。なのに数日後たちまち動く青山君。うらやましさと怒りで割りばしも二つに割れないわれら三人……
考えてみればひどい劇団だった。若さとはそんなものよね、と人は笑うけれどつぶさに思い出すとグロテスクで見てられない。そのだらしない人間模様の基礎は私も一緒になって作ったのだからと当時は嫌悪より反省する気分が強かったが、確かに空気は変わっていた。もう「僕たちの劇団」ではなくなったんだよね、と誰も口には出さなかったけれど後輩達の作るなじめない空気からわれら三人は次第に遠ざかるようになった。
……こんなのは予想していなかった。もっと感動的でさわやかにお芝居を終えるはずだった。でもまぁいいや。……どうせもうすぐ就職だし、演劇なんて完全にやめてしまおう。でもやめる前に、遺書のように、なにか書き残そう。だってせっかく一生懸命やってきたんだもんなぁ…出来はどうでもよかった。なにか書き残せればよかったのだ。書いては挫折し、書いては挫折してまだ一回も最後まで書ききったことがなかった台本を、なんでもいいからとにかく「完」というところまで書ききって、きっぱりと劇団の仲間と、演劇と、にさよならしたかった。あとは着実で安定したサラリーマンの人生が待っているのだ。もうこんなヤクザな興奮とは無縁の一生を送るのだ。半ば解放感に近い感情があって、私はちょっとは楽しい気分で、そう、大学の図書館に通ったのだ。
……友達はいなかった。どこを見ても。冷房の音しかしない、清潔な広い図書館の奥には髪の長い女の子がいる。司法試験の勉強だろうか。私はノートに文字を書いたりその髪を観賞したりちっとも集中できないで、でも時々はかわいかった後輩達の顔を思い浮かべて泣けてきたり、……さえない記憶しかない。 あれが第一作。今私は第三十三作の脚本にとりかかろうとしている。演劇と縁を切るはずがすっかり抜けられないでいまだに続けている。時々人からほめられるけれど、たいして根性を出して頑張った、という記憶はない。あのときのさえない感情、ちょっとは楽しい気分、それがいつまでも忘れられなくて続けてきているだけだ。だけど一つ変わったことがある。あの時ほしかった仲間が今はいるのだ。劇団の仲間。なんでもいいから一生懸命やれば仲間はできるものです。それがいろんな受賞歴よりもなによりも今の私の誇りです。
Page Top