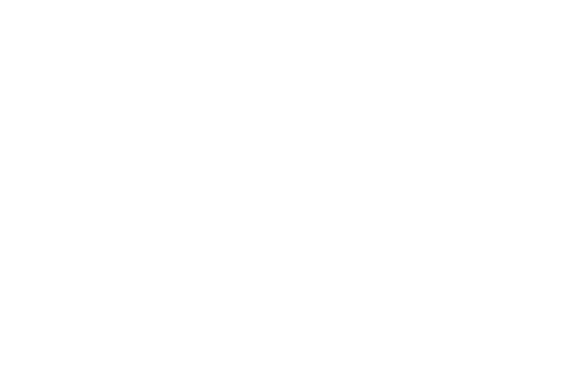2013年7月6日
西陣から社会を考える~ものづくりの大切さ~
髙橋 孝三さん 【元西陣織工業組合専務理事】
 |
今回、お話をお伺いしたのは、西陣織工業組合専務理事を務めておられた、髙橋孝三さんです。現在は、花園大学などで、「西陣学」の講義をされています。
御年80歳になられますが、とてもお元気な印象をもちました。夏の暑い日にも関わらずネクタイを締め、背広を着て、北青少年活動センターへ足を運んでくださいました。博識な方で、いろいろなお話を伺うことができました。
まずは、「江戸時代、京都は日本一の工業都市であったのですよ」との言葉からお話が始まりました。「江戸時代、京都の禄高(ろくだか)は、わずか十万石ほどにすぎなかったのに、三十五万もの人口を支えてこられたのは、当時、京都が、ものづくりが盛んな産業都市でもあったからです」そして、「千年の都から生まれてきた数々の知恵が巧みな技となって、今、京都が誇る伝統産業となって伝えられているのです」と髙橋さんの話が続きます。
長い間、伝統産業は全て、京都の地域で生産されていました。戦後、高度な経済成長の恩恵を受け、西陣の出荷額が三千億円にもなった時には、人手不足もあって、盛んに地方、例えば丹後などへ、出機(でばた)として生産の拠点を移しはじめたのです。いわゆる、アウトソーシングです。西陣の地域には、お金が落ちてこなくなります。商店街がさびれ、徐々に活気を失ってしまいました。
また、グローバル化の名によって、アウトソーシングは、中国などの諸外国にまで及ぶようになってきました。そうなると、伝統技術までもが流失し、産地が崩壊してしまいます。髙橋さんは、「伝統産業こそ、地域の歴史や文化を生かして地元で作られるべきだ。それがグローバル化にも通用するのです」と強調されました。

次に、西陣の伝統技術の中味や紋織物の特性についての話をしていただきました。紋図や紋紙の見本を見せていただき、「織物を織るのはとても繊細な作業で、デザインや糸づかい、色彩など、それぞれの持ち場で感性を生かすことによって、その価値が決定されていくのです」と話されました。
西陣の地域については、ご近所づきあいが強いため、住みよい町ではありますが、反面、プライバシーがあまりありませんでした。若いころの髙橋さんはそれが嫌いでした。しかし、歳を重ねるごとに西陣が好きになり、「今となっては、他の地域には住みたくない」と話され、西陣地域への愛が伝わってきて、とても素敵でした。
また、髙橋さんは「ものづくりは、個性を表現し、希少性を重んずる一方、社交性、普遍性といったものを持たなければならないという葛藤の中から生まれてくるものである。それは人生にも通用する」とも言われました。京都の西陣という伝統ある街で、ものづくりに携わり、生活されてきた髙橋さんならではのお言葉は心に響きました。
「現代は、グローバル化に名をかりて、金融市場で大金を稼げるような時代で、ものづくりの重要性が失われがちです。そして、結果的には経済の足腰が弱くなってきている」と続けられました。

髙橋さんは、「今の若者は幸せだが、人とのつながりが薄まり、気の毒でもある」とおっしゃいました。ずっと、長い間、西陣産業を見守ってこられた髙橋さんのその言葉にはとても重みがあり、ものづくりが持つ重要性を知ることができました。
私たちが、人とのつながりを、一度立ち止まって考えてみるいい機会になりました。
(執筆者:今井 大揮,荒木 柚乃)
*その他のスタッフの感想*
・「ものづくりの大切さ」を教えていただきました。西陣でつくられる織物は、歴史であり暮らしを支えるとても重要な位置を占めているのだと感じました。また、時代とともに、「変わらない部分」と「変わっていく部分」があったから、伝承ではなく伝統として受け継がれているのだと思いました。(日裏 瑠奈)
・西陣に対して、マイナス・プラス面の様々な思いを伺うことができました。西陣織は感性が大事で、3代も続くことは難しいということを知り、伝統産業の厳しさを感じました。髙橋さんは、誇りや自分の思いというものを強く持っていらっしゃる素晴らしい方でした。(石原 真理絵)
・髙橋さんの「ものづくり」に対する想いがとても伝わってきました。2時間もお話を伺ったのに、まだまだ話し足りないとおっしゃっていたことに驚きました。(西田 拓真)