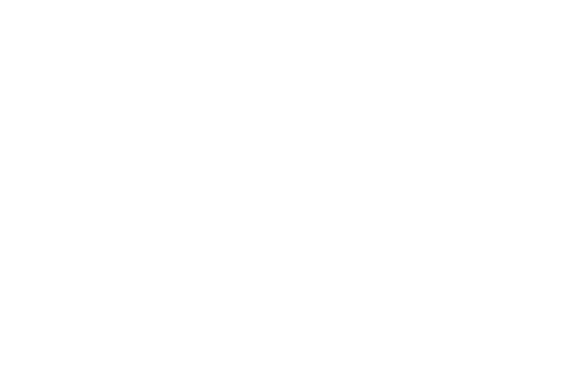西陣ひと・まち・もの語り㉒
2013年6月13日
2013年6月13日
日々の活力は仕事から
山中 笑子(えみこ)さん 【衣師(ころもし)】
 |
堀川寺之内交差点から、少し東へ入ったところにある一軒家。呼び鈴を鳴らし、出迎えてくださったのは、とても77歳とは思えない、シャキシャキした印象の山中笑子さん。現在、一人暮らしの山中さんは、お寺へ卸す袴の仕立てをされておられます。なんとこの道40年ほどになるそうで、今でも、1か月に10領ほどの袴を仕立てておられるそうです。この袴の仕立て作業は、「お勤めと違って、家に居ながらいつでもできるのが楽だ」、と山中さんは笑います。ほかにも西陣年功会委員や、上京老人女性会委員もされており、めまぐるしい毎日を過ごされています。
山中さんは丹波のご出身で、この西陣地域へ嫁いで55年になるそうです。男の子2人、女の子1人の3人のお子さんを育て、幼稚園の先生もされていました。子育てに一段落ついたころ、袴を仕立てる仕事を始められたそうです。最初は見よう見まねで裁断の手伝いから始めたこの仕立て作業も、今では1領につき、3時間半から4時間ほどで出来上がる、とのことです。織物の紋の見え方が袴によって決まっており、少しでも間違えると大変なことになるそうです。山中さんのおばさまは、時代祭や葵祭りなど、袴の需要が多い時期には徹夜で仕事をされたそうで、おばさまのそんな姿を見ながら、仕立ての技術を磨かれたそうです。山中さんは、作業中の正座も全く苦にならないそうで、さらには今でも裸眼で針に糸を通すことができるそうです。本当にお元気で活力のみなぎるお方であると感じました。
山中さんが作る袴は、決してひとりの力で出来上がるわけではありません。糸を染める人、反物を織る人、そして山中さんのように袴へと仕立てる人。この仕事のラインは固い信頼関係で結ばれ、そのつながりが薄れることは無いと言います。人と人とのつながりが、西陣地域の産業を支えているのです。しかし、そんな地域の結びつきも最近では弱くなってきている、と山中さんは語ります。昔は、織屋さんが軒を連ね、機を織る音が絶えることはなく、その音が大きいためにおしゃべりすることもできなかったそうです。けれども今や夢のあと。マンションやスーパーが立ち並ぶ現在の西陣地域においては、生活は便利になったかもしれませんが、ご近所づきあいは昔ほどではないそうです。「それもこれも時代だからしょうがない」、と山中さんはさびしそうな顔をされました。
 |
山中さんは、「今の袴を仕立てる仕事は80歳まではやりたい」、と意欲を見せてくれました。また、「お寺の行事がある限りはいくらでもできる」、とおっしゃっていました。この仕立て作業は、お金がもらえるという実益の面はもちろんですが、ご自身に人生のハリを与えてくれる存在だそうです。「責任あることをしていると気持ちがしゃんとして、元気が出てくる」と山中さんは言います。この仕事こそが、山中さんの若さの秘訣かもしれません。
最後に山中さんには今の若者に対して、「もっと自分の知らない世界に飛び込んで覚えるべき」というメッセージをいただきました。人生の大先輩からのお言葉、しっかりと心に留めておきたいと思いました。 (執筆者 今井大揮)
<感想>
・初めてのインタビューということで少し不安や緊張はあったのですが、法衣製作の奥深さや、それに従事なさった経緯など親切に教えて頂き、結果としてもとても興味深いインタビューになってよかったです。(小山敬太郎)
・とても気さくな方で、法衣についてや、引っ越して来た頃の西陣の様子など貴重なお話をいただき西陣の街にさらに魅力を感じました。ありがとうございました。(山中美穂)
・初めてのインタビューでしたが、仕事のことや地域のことについて、興味深いお話を伺えて良かったです。特に、「責任あることをしているとしゃんとする」という言葉がとても心に残りました。
(西田拓真)
・山中さんは仕事に地域での活動に、充実した日々を過ごされている方でした。温かく迎えて下さり、朗らかなお人柄が伝わってきました。見せて頂いた仕立の生地もとても綺麗でした。(石原真理絵)