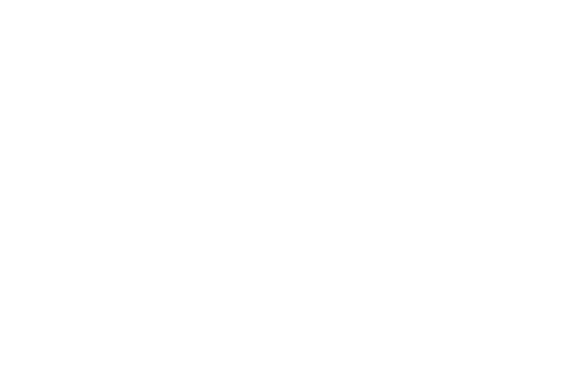西陣ひと・まち・もの語り⑲
2012年10月16日
糸染めにおける色づくりの工夫
福田義久 さん 【福田染工】
今回は、濱卯染工業の岡本さんからのご紹介で、同じく染業を営む福田染工の福田義久さんにインタビューを行いました。千本寺之内通りを東に入り少し上ったところに、閑静な住宅と並んで、営まれているのが福田染工です。
福田染工は創業110年で、他のところと比べると、200年というところもあるので、それほど長いわけではないそうです。福田さんは、幼少期からご両親のお手伝いをしながら、糸染めに触れ、高校で染色を専門とする学科で3年間修業した後、18歳から職人となり、そこから一筋で現在に至っているそうです。
長年の経験に裏打ちされたカンが必要な染色技術
染業は織元の指定した通りに糸染めを行わなければなりません。そのため、長年の経験が必要で、用途や耐久性、染料の種類などがすべて頭に入ったうえで、分量などはカンであるということです。そして、西陣織は、20以上の工程があるので、後ろで待つ工程をも背負っているという責任の大きさも強調しておられました。染色作業については、少しずつ濃度を合わせていき、色については出たとこ勝負になるのが、手仕事の大きな特徴です。


実際に色を合わせていく作業を見せてもらいましたが、私たちにはすでに目標の色に出来上がっているように見えても完璧には一致していないとダメであるということを実践の中で教えていただきました。よく見ると、糸の束になっている外側はきれいに染まっているのに対し、内側は、まだ十分に色が染まっていませんでした。
仕事における近年の変化
染業を営まれていての昔から今への変化をお伺いしたところ、先代の父の代では帯屋に納品するのが仕事のほとんどであったが、ウェイトがここ10年から15年で金襴や、人形の着物、掛け軸の糸染めなどが増えてきて、色の発色の仕方が違い、相手先のこういう色にしてほしいという意向がうまく反映できないこともある。そのニュアンスと実際に染めた色が合っているのかどうかが難しいそうです。
そんななか福田さんは10年ほど前に色の変わる染めを開発しました。これは麹塵(きくじん)染めや鳩羽鼠(はとばねずみ)という特殊な技法で、例えば、日光や室内光が当たることで、糸の色が変化するというものです。これは、スーパーの肉の陳列の工夫と同じで光源に照らされることで鮮度のよい色の肉に見えるよう工夫されています。糸の色も同じように光源によって良い色に見える工夫がなされているのです。 30年、40年前であると、土日がないくらい朝から夜まで糸染め作業が続いていることもあったそうです。それに比べると、そこまで忙しい状況ではなくなってしまったといいますが、福田さんは、「この色が変化する技法を活用した新たな使い道が見つかれば」とおっしゃっていました。
若者への技術指導
後継のご指導にも積極的で、ボランティアとして若い人の支援に従事しているそうです。30歳のころから組合で希望者に染業を教えていて、 7年前ごろからは染色技能検定の検定委員をつとめているそうです。後継者については、親がつくった家を息子の代が継いで残していってほしいというのが理想ですが、現実としてそううまくいっているところはない。後代への技術指導についても、「なかなか短期間で習得できるような技術ではないために、途中でやめてしまわれる可能性もあり、簡単に教えることはなかなかできない」と考えておられました。一方で、若い人が染色だけを志すことができる状況にないことも承知しておられ、こうした部分も含めてなかなか後を継ぐような若者があまりいない現状へのもどかしさを少し感じているように思いました。
現代の大量生産の時代にあって、産業としてはかつてのにぎわいがないのは事実かもしれませんが、だからといって全く生産が必要なくなってしまうということはあり得ません。
西陣織という技術は機械によって簡単に生産することができないものだからです。
だからこそ、いかにこの技術を継承していくかの仕組みづくりが今後より早急に必要となると思いました。
(執筆者 赤松崇志)