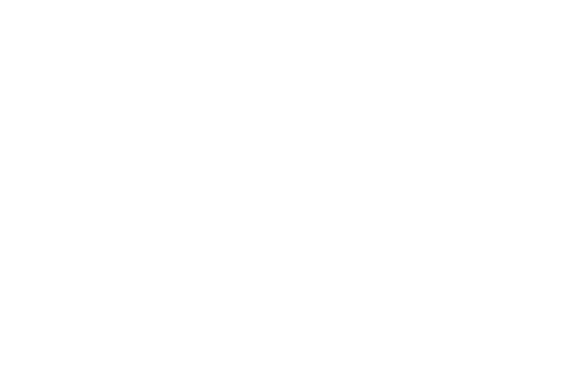西陣ひと・まち・もの語り⑰
2012年8月6日
町家と共に歩んできた「陶芸」への途
生駒啓子 【陶芸家】
陶芸といえば近畿地方では清水焼、信楽焼などが有名ですが、生駒さんは湯飲みや器などの実用品でなく、芸術性に重点を置いた立体作品を主に制作しています。大学院卒業後に西陣の町家へ移り住み、作品の制作販売をされると共に、自宅で陶芸教室を開講。更に、大学でも講師として学生の指導に当たるなど、多岐に渡って精力的な活動を行っています。
はじめて陶芸に興味を持ったのは、高校時代でした。

生駒さんは子どもの頃から絵を描くことが好きで、絵画教室に通っていました。併設していた定時制高校に陶芸のできる場所があったので、一度施設を借りてやってみたことがあったのです。すると、平面の絵と違って、立体として形になることの新鮮さや面白さに惹きこまれ、陶芸の世界へ足を踏み入れました。ピアノも得意だったので、進路選択の際は音楽か陶芸か、どちらの道へ進むか迷いましたが、つくった壺が高校の陶芸展で入賞したことを機に、陶芸を学べる京都精華大学へと進路を決めました。
大学では毎日朝9時から夜10時まで大学に詰めて、日々クラスメートと陶芸に打ち込みました。熱心な学生が多く、連日連夜、家族と過ごすほど長い時間を一緒に過ごしてきたため、当時の友人とは、今でもよく連絡を取り合うほどの仲なのです。その後、同大学大学院、修士課程へ進学して発展的な指導を受ける一方で、カルチャーセンターで陶芸家の方のアシスタントとしてアルバイトを始めました。アシスタント業務をこなしてゆく中で、独立に必要な窯を買うための資金を貯めました。
生駒さんが西陣に興味を持ったのは、1996年でした。修士課程も卒業が近づいてきた頃で、陶芸家として独立を考えていました。陶芸の作業ができる家を探していたところ、ある日美容院で「西陣地域に良い空き家がある」という情報を耳にしたのです。その翌日、黎明期の「町家倶楽部ネットワーク」を紹介する記事が偶然にも新聞に載っていたことから、西陣で家を探してみようと思いました。
町家倶楽部の紹介で現在の素敵な町家が見つかり、大学院卒業と同時に入居、陶芸家として独立しました。それからは一階を陶芸スペースにして教室を開き、二階を住居に日常生活を送っています。
独立してからは、自分で仕事をつくる必要がありました。カルチャーセンターで様々なノウハウを学んでいたので、それを活かして陶芸教室を開き、作品の販売も行なっていきます。作品の中では白熱球と合わせる黒い照明具と、花器が人気だったので、よくつくっていました。
伊賀に、天保3年(1832年)から続いている由緒正しい「長谷園」という窯元があります。こちらは「土鍋ブームの火付け役」としてもテレビで取り上げられる所ですが、生駒さんが学生時代につくった照明具を購入し、飾って下さっていました。とても有名な窯元なので、デザイナーや世界的インテリア雑誌『エル・デコ』なども含め様々な来客があり、そこで作品を見て、気に入って下さった方から「同じものが欲しいのですが」という風に依頼をされることも、しばしばありました。
独立して感じたことは「先生や上司のありがたみ」でした。自分=社長なので、自己管理が大変難しいのです。さぁ、今日はこれをやるぞ!と決めていても、友達から。 「今日、会わない?」と言われた時、まぁ……今日はいいかなっ?と思ってしまい、どんどん予定がずれこんでしまうことも次第に、誘われても「この日は用事があるので」と言って、自分に厳しく仕事をしないといけないということが分かってきました。
「今日、会わない?」と言われた時、まぁ……今日はいいかなっ?と思ってしまい、どんどん予定がずれこんでしまうことも次第に、誘われても「この日は用事があるので」と言って、自分に厳しく仕事をしないといけないということが分かってきました。
 「今日、会わない?」と言われた時、まぁ……今日はいいかなっ?と思ってしまい、どんどん予定がずれこんでしまうことも次第に、誘われても「この日は用事があるので」と言って、自分に厳しく仕事をしないといけないということが分かってきました。
「今日、会わない?」と言われた時、まぁ……今日はいいかなっ?と思ってしまい、どんどん予定がずれこんでしまうことも次第に、誘われても「この日は用事があるので」と言って、自分に厳しく仕事をしないといけないということが分かってきました。「でも、そうだなあと思いながら、ちゃんと守れているかどうかは別よ(笑)」――生駒さんはそう言って、表情を緩めました。
1999年、ひとつの転機が訪れました。ニューヨークの都市プランナーから「エクスチェンジプログラム」というお話をもちかけられたのです。ニューヨークのピークスキルという街では「アーティスト居住区」という特区が設置されています。アーティスト居住区では、街づくりの一環としてアーティストを誘致。ピークスキルに住居を構えて芸術活動をしてもらおう、という取り組みがなされていました。そうした取り組みは、西陣における町家倶楽部の活動とコンセプトが似ていたため、都市プランナーの方が西陣へ視察に来られたのです。その際に生駒さんの立体作品を見て、「エクスチェンジプログラムという形で、一度ピークスキルに来ないか?」と声がかかり、なんと2ヶ月間、ピークスキルに住むことになりました。
ピークスキルでの生活は、日常から一転して「自由な2ヶ月」でした。滞在中は、自分の好きに時間を使って良かったのです。日本語から解放れたことも新鮮な毎日をもたらし、かつて経験したことのない楽しさがありました。生駒さんは滞在中に作品を制作して、発表をすることを目標に日々活動していきます。英語やアメリカ文化に戸惑うところもありましたが、悩む時間もないままに行動していき、ニューヨークにいる間に作品をつくりあげました。
帰国後は、京都芸術大学の大学院・博士課程に進みました。その頃もカルチャーセンターでのアルバイトは続けていたので、自ら陶芸教室を開いて、アシスタントも行なって、更に京都芸大にも通うというタイトなスケジュールをこなす毎日が続きました。
――博士課程を卒業してから数年が経ち、母校の京都精華大学で教鞭をとることになって、また数年の月日が流れました。
生駒さんが陶芸を始めてから現在まで、作品づくりに関して大切にしている美学があります。それは、「他の素材では出せないような、粘土らしい質感を美しく作品に宿したい」ということ、そして「作品の目の前に立った時に、静かなパワーを感じられるような作品づくりをすること」です。今は制作上の悩みがあって、なかなか個展が開けないそうですが、それを解決するために、ここ数年は絵の勉強をしているほか、陶芸家が集まる勉強会にも積極的に参加したりしています。

最後に、生駒さんはこのように私たちにお話下さいました。「生活自体は楽しいし、不満はないんです。人はなんて言うかわからないけど、自分の中でもっと良いものをつくりたいっていう気持ちがあって。それは納得いく最後はないんだと思うけど、40歳を機にもうちょっとパワフルに活動をしたいなって思っています」
陶芸の世界には、バイブルがありません。決まりごとは全て、師匠から弟子へ口伝で伝えられていきます。更に、決まりごとすら「模範のひとつ」くらいの意味合いで、守らずに自分の思う通りにつくっても良い。ひとつの作品の背景には、正解のない世界で粘土と相対し、自分の感覚を研ぎ澄ませながら試行錯誤してきた、膨大な日々の堆積がありました。
創作と向き合う時は、常にひとり。気さくでお優しく、柔和な笑顔が素敵な生駒さんですが、生涯、自らの作品づくりを突き詰めてゆこうとするストイックな背中と、様々な路を経た結果産み出されてきた作品に対して想像を巡らせると、畏敬の念を感じずにはいられませんでした。
(執筆者:丁 芸,神保)