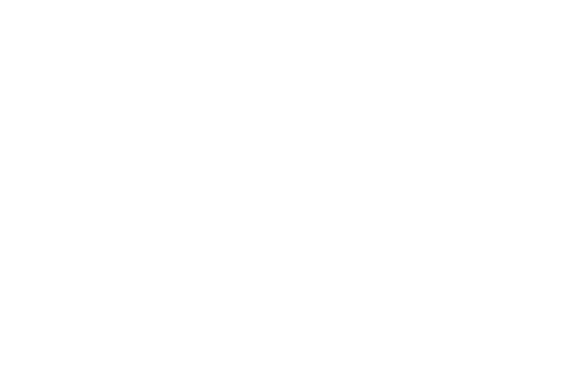西陣ひと・まち・もの語り16
2012年7月31日(火)
西陣で光る職人の技
岡本 祝郎さん(濱卯染工場)
今回、インタビューを受けて頂いたのは西陣地区で染物業を営んでおられる岡本さんです。
インタビューに行った時には岡本さんは弟さんと二人でお仕事をされていました。工場は、100年以上前からあるそうで、歴史を感じる建物でした。

かつてはこのような染業を営んでいる人たちは全国各地で見られたそうですが、今では京都の西陣以外の地域ではほとんどが衰退してしまったそうです。西陣地区でも最盛期には200軒ほどあった染屋も今では70軒ほどに減ってしまいました。
岡本さんの家では先代からあわせて150年ほど西陣地区でお仕事を続けられているそうで、さすが京都の伝統産業だなと思いました。
今回は、岡本さんから普通に生活していても聞くことのできないような貴重な話をたくさん聞くことができました。

簡単に自己紹介をした後に実際に絹に色を付ける作業を見せていただきました。

作業は、大まかに三つの工程で行われます。まず、鍋の中に染料を入れ、煮詰めて温度を60度から90度くらいに上げます。その中に絹を入れて染色します。絹は安い中国産やブラジル産のものが多いそうです。次に染めたい色になるまで絹を染料につける作業を繰り返します。この色を組み合わせる過程が一番難しいそうで、気分で色が変わってしまうこともあるそうです。岡本さんは目分量で染料を調節されていましたが、僕たちには微妙な色の違いはほとんど分かりませんでした。見事な職人技でした。
はじめは茶色だった絹は、この作業を繰り返すうちに次第に焦げ茶色になりました。僕たちも染める道具を持たせてもらいましたが、思った以上に重く染める作業はかなり重労働です。夏はとても暑くて大変だろうなと思いました。そのあとに絹を乾かす作業を見せてもらいました。専用の機械を使って脱水と水洗いを繰り返し、絹を竿に干して乾かしたら完成です。

1つの染物が完成するまでには大変な労力がかかっていて染物の仕事はとても大変な仕事でした。
岡本さん自身は高校を卒業してからはずっとこの仕事をなさっているそうですが、これまでやめようとかしんどいと思ったことは無いそうで、これは素晴らしいことだなと思いました。自分が染めた色を喜んでもらえることが仕事のやりがいだそうで、今までに相撲で使うしめ込を作ったこともあるそうです。話を伺ううちにこの仕事に対する誇りが伝わってきました。
染業だけでなく、西陣地域の産業全体の課題としてはやはり、後継者問題があります。岡本さんは、染業や西陣織産業自体は無くなることは無いとおっしゃっていましたがやはり後継者不足は深刻なようです。
最後に僕たち若い世代へ「何か一生懸命になれることをどんなことでもいいので探してほしい」というメッセージをもらいました。仕事を本当に楽しんでおられる岡本さんのこの一言はとても印象に残りました。岡本さんのように自分がこれだと思えるような職業に僕もつくことができればいいなと思います。(佐藤 有泰)
ほかのスタッフの感想
・染業自体を初めて知り興味が出てきたと同時に岡本さんが優しく「染業がはやっていってほしい」という気持ちが胸に熱くきました。今回の活動で染業、そして岡本さんに会えてよかったと思います。
(中尾)
(中尾)
・初めて実際に作業している中へお邪魔させていただきましたが、この夏の暑い中でも、熱心にお仕事をなさっている姿と、それに対して別にしんどくないと言っていた言葉が印象的でした。また、後継者不足も深刻だと聞き、この伝統産業をどう残していくかを我々若い人達がより考えなければいけないと感じました。(赤松)