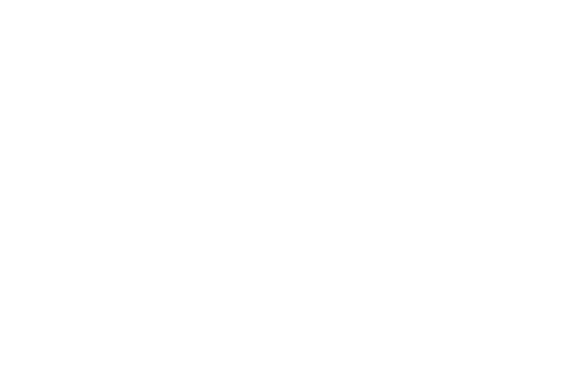町家の「宝石店」に輝くもの
【京都西陣蜂蜜専門店ドラート 店長 大久保 ひとみさん】
 |
昔ながらの町家が建ち並ぶ紋屋図子(もんやずし)の中腹に「三上家路地」はあります。三上家は、江戸時代に六家存在した御寮織物司(ごりょうおりものつかさ)――平たくいえば宮中御用達の織元の中で、唯一現存する織元です。かつて紋屋町の周辺には三上家も含め、御寮織物司が五家まで集住していた時期があり、西陣を代表する一帯でした。そうした歴史から、三上家と紋屋町は西陣の発展に深く関わってきた場として、今でもドラマ撮影、ライトアップ企画など、様々な場面で利用される傍ら、観光で訪れる人も後を絶たない場所となっています。
さて、今回のインタビュー先は名所、三上家路地の一角にひっそりと佇むお店「京都西陣蜂蜜専門店 ドラート」です。――町家風情のある外観から一転、入った瞬間目に飛び込んでくるのは、橙黄色のあたたかい灯、整然と並んだガラスのデキャンタ、様々な色合いで絢爛と輝く蜂蜜のディスプレイ。「ニューヨークの宝石店を思い描いた意匠」ということで、文字通り宝石箱のように美しい空間には、たおやかで優しい時間が流れています。お話を伺ったのは、店長を務めていらっしゃる素敵なご婦人、大久保ひとみさんです。
 |
大久保さんは、ドラートでお仕事をされて7年になります。店舗の隣の陶芸教室に通っていらっしゃったことがきっかけで、ドラートでお仕事をされるようになりました。お仕事をされるようになってすぐ、おめでたいことにオーナーがご懐妊されて「これから店長よろしく!」という方向に話が運んでゆき、それからは独学で必死に蜂蜜の勉強をされたという経緯がありました。「――けど、やりだしたら面白いんですよ。すっごい奥が深いんです。蜂蜜の世界も、ミツバチも」と語る大久保さんは、今ではご自身で養蜂もされるほど、蜂と蜂蜜の虜になっています。
蜂蜜専門店というと、普段なかなかお目にかかる機会はないかもしれません。実は市販の蜂蜜は単花蜜と百花蜜に分類され、単一種の花からとった蜜が単花蜜、複数種の花からとった蜜を百花蜜と呼びます。単花蜜は希少なため、百花蜜と比べてお値段も少し高くなりますが、花の種類によって味の個性が明確に表れる特徴があります。私も単花蜜の桜を味見させて頂きましたが、口の中で味が2段階、3段階と変化するような奥行きを持った味わいで、これが蜂蜜の美味しさなのかと驚嘆しました。店内ではどなたでも、様々な種類の蜂蜜をテイスティングできます。蜂蜜が苦手な方でも、単花蜜の蜂蜜をご試食なさると「美味しい、いっつも食べてるのと違うなあ!」とおっしゃってくださるそうです。「町家のこぢんまりとした店で、路面店と違って奥まった所にあるからゆっくりしてもらえる。蜂蜜好きな方だけでなく、町家が好きで来られる方に対しても蜂蜜の楽しみ方をご提案できることは、建物のおかげですね」と笑顔でお話下さいました。
意外にも、日本で蜂蜜が普及したのは戦後のことでした。昔は今より精肉の質が悪く、あまり美味しくないお肉を美味しく食べられる方法が求められていました。ある時、蜂蜜をお肉に塗 るとタンパク質が凝固しづらくなって柔らかく焼き上がること、そして蜂蜜がカラメル化することで、外はパリッ、中はジューシーに焼けるという革命的な発見があったことで、蜂蜜が一般に普及して、現在までにバラエティに富んだ蜂蜜の使い方ができたという歴史があったんですね。皆さんご存知でしたか?
 |
店内では、私達が普段見聞きしないような蜂蜜も沢山販売されていました。例えば、パラシュというインドの蜜は、非常に栄養価が高く、インドでは薬局に売っている蜂蜜です。少しバルサミコ酢に近い味と聞いて試食もさせてもらいましたが、食べた瞬間確かに「すっぱッ!」という声が出そうになり、蜂蜜とはなんて味が多様なのだと感じました。このパラシュの最大の特徴は、養蜂によって採取された蜂蜜ではなく野生の蜂蜜である所で、木や岩の上に自然にできた巣を、インドのハニーハンターが蜂に刺されながらまるごと取って、蜂蜜を採取するとのことです。命がけの大変な作業によって採れる希少な蜜なので、世界に広めるべきだということでインド政府が介入して採取から販売まで行なっています。
また、ニュージーランドのマヌカハニーも、珍しい蜂蜜のひとつです。ニュージーランドは、蜂蜜の年間国民消費量が世界一と言われるほど蜂蜜が生活に取り入れられていますが、カマヒ、レワレワなどの固有植物が多く、日本とは花の種類も蜂蜜の種類も少し違います。その中で最もポピュラーな木がマヌカといって、そこからとれる蜂蜜がマヌカハニーと呼ばれ、蜂蜜の中でも殺菌性が一番強いので、口内炎や、喉が痛い時などに使うと良いと聞きました。
 |
他にも大久保さんの蜂蜜のお話はとても興味深く、蜜蝋はクレヨンや手術用の糸に用いられていること、実はイチゴや梨の栽培にまでミツバチが活躍していること、蜂蜜とチーズの相性は最高に良いことなど、ミツバチと蜂蜜にまつわる様々なエピソードをユーモラスに語って下さいました。単なる断片的知識として知るだけではなく、「体験」から「実感」して得た経験的知識を大切にして、ご自身で養蜂までされるようになったということで、その蜂蜜に対する真剣さに大変感銘を受けました。
付記
 |
大久保さんはかつて、20年間手描き友禅の職人をされていました。友禅は西陣織と同じく、現代的生活との間で転換期を迎えている伝統工芸のひとつです。――往年の手描き友禅への情熱は現在、蜂蜜に対するこだわりと探究心へと形を変えて、その朗らかなお人柄と共に、西陣の町家の一隅を温かく包み込んでいます。たとえ伝統や文化は失われたとしても、それらを引き継いできた職人さんの心粋(こころいき)は変わらず輝いているんだなと、そんな風に感じた梅雨の一夜でした。 また、この取材は営業終了後の夕刻からさせていただきました。取材に快く応じてくださったこと、そしてお仕事が終わってお疲れのところ、時間を割いて私達に貴重なお話をしてくださったこと、感謝致します。
執筆者:神保
取材者:赤松崇史、神保、丁芸、早川みなみ、細田祥子
☆スタッフの感想
・西陣という場所に興味をもって来たことがドラートを知るきっかけになる人が多いと聞いて、意外でした。でも、地域が守ってきたものから新しい出会いがどんどん広がっていくのだと思うと、楽しい場所のように感じます。大久保さんがオーナーの方と出会ったように、これからも出会いがたくさんある場所であってほしいと思いました。(細田)
・宝石店×蜂蜜×町屋と、普通なら関連のない組み合わせが同じ空間に広がっていて、不思議な場所だと思いました。蜂蜜に興味があって来た人は町屋やキラキラした雰囲気という別の良さに出会える、西陣のこのお店だからこその魅力があり、素敵な場所だと感じました。(早川)
・こんなたくさんの種類の蜂蜜は人生で初めて見ました。いろいろな蜂蜜を試食して蜂蜜に対して新しいイメージが残ってきました。本当に立派な感じのお店で、西陣地区でこのような蜂蜜専門に販売しているお店があってすごくいいと思いました。(丁)
・きれいに並べられた蜂蜜について、丁寧にひとつひとつ説明してくださった姿が印象的で、蜂蜜の奥深さを知ることができました。このようなオシャレな町屋が増えていくと、より西陣地域の魅力は増していくのではないかと思いますし、その魅力をみんなで共有していくことが大切だと思いました。(赤松)