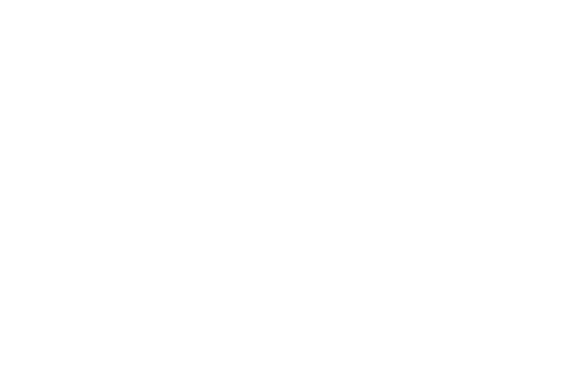「伝えたい。考古学の魅力」
京都市考古資料館館長 辻 純一さん
今回、京都市考古資料館で館長を務めている辻 純一さんにインタビューを行いました。![GEDC0840[1]](http://www.jade.dti.ne.jp/%7Enishiho/zigyo/2010/hitomati/clip_image002.jpg)
地下鉄今出川駅を出て、車がたくさん通る今出川通りに沿って歩いて行くと、他とは少し違って古めかしく、趣のある建物が見えてきました。正面には大きく「西陣」と彫られた「西陣の碑」が建てられている、そこが京都市考古資料館でした。
京都市考古資料館は、昭和51年に設立された「財団法人京都市埋蔵文化財研究所」の発掘・調査・研究の業績を発表・展示するため、昭和54年に設立されました。建物は大正3年に西陣織物館として建てられたもので、市の文化財に指定されています。
資料館には、年間およそ2万人の人が訪れます。合計で約1,000点ある展示品は、約2万年~200年前くらいのものまで、京都市の通史を一通り見ることができます。
館長である辻さんは、京都市埋蔵文化財研究所の職員でもあり、発掘調 査に携わっています。辻さんがこの仕事を始めようと思ったきっかけは、大学生の頃に始めた平安京調査会の発掘調査アルバイトでした。初めて参加した発掘が とても楽しく、もっとしたいと思うようになったそうです。そして、大学卒業後にすぐに研究所の職員になられたとおっしゃっていました。
辻さんは、このような調査によって遺跡から発掘されたもの1つ1つを分析することによって、その時代の背景がわかり、「本当の意味での歴史」を知ることができるといったところに考古学の魅力を感じて いると楽しそうにおっしゃっていました。そして、その魅力を、資料館を通じてたくさんの人に伝え、考古学のファンを増やすことが目標の一つでもあるそうで す。
しかし、資料館の現状についてのお話を伺ったところ、現在の資料館には高齢者や、授業の一環で訪れる小中学生、観光客が多く来館していますが、間となる20~30代の人が少ないので、その年代の人にどのようにすれば興味をもってもらえるのか、来館者数自体をどうすれば増やしていけるのかということ等に頭を悩ませておられました。
さらに最近では、団体の小中学生も減少傾向にあります。そこで、辻さん は若者のファンを増やすための工夫として、お土産がない代わりに、簡単な拓本をお客さん自身に採ってもらい、それを記念として持って帰ってもらう、といっ たことを検討しています。また、訪れる人に対する資料の説明ができる人材がほしいということで、ボランティアでの業務参加をしてもらう計画も考えていると おっしゃっていました。大学生に興味をもってもらうためにも、大学にも声かけをしているそうです。そして、これからはもっと地元との関わりも大切にして、 何かを一緒にしていきたいと考え、史跡ウォークラリーなどを実施し、人を呼び込めるような工夫を考えているそうです。
![GEDC0836[1]](http://www.jade.dti.ne.jp/%7Enishiho/zigyo/2010/hitomati/clip_image004.jpg) 辻さんは、発掘調査や、考古資料の話をされている時、とてもいきいきとしていました。また、館長という仕事を通して、「最近は、“暗 記ばかりの歴史”になってしまっているので、考古資料から本来の歴史を知ってもらうことにより、その面白さを伝えていくことが自分の使命のように考えてい る」とおっしゃっていました。
辻さんは、発掘調査や、考古資料の話をされている時、とてもいきいきとしていました。また、館長という仕事を通して、「最近は、“暗 記ばかりの歴史”になってしまっているので、考古資料から本来の歴史を知ってもらうことにより、その面白さを伝えていくことが自分の使命のように考えてい る」とおっしゃっていました。
このように、辻さんの考古学に対する思いや、課題に向き合う姿勢、そ して、その解決に向けての努力があるからこそ、今の考古資料館があるのだと思いました。そして、そこがたくさんの人に考古学の面白さを伝えることのできる 大きな1つの発信源になっていくのではないでしょうか。
(執筆者:細田・布川)
☆他のスタッフの感想
辻さんが、楽しそうに遺跡の話をされていたのが印象に残りました。
お話から、展示物の楽しみ方を知り、実際に器などに触ることも出来ました。また、展示物の見せ方についても考える機会を得ることができました。
考古学に惹かれる理由が、「昔の人の生活や考え方を知ることができる」という、私たちの活動にも通じるものがあって共感しました。
☆京都市考古資料館
〒602-8435 京都市上京区今出川通大宮東入る