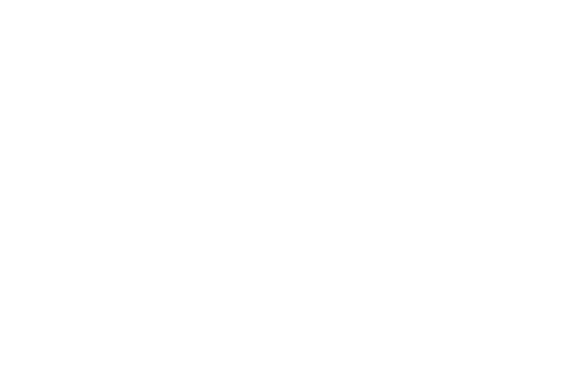2014年5月11日
絣織の記憶を受け継ぐ
徳永 弘さん 【絣(かすり)加工師・伝統工芸士】
28回目は、絣加工師の徳永弘さんにお話を伺いました。絣織物の糸を加工するお仕事をしておられます。
徳永さんは滋賀県出身で、現在79歳。階段を楽々と登るとても元気な方で、すてきな笑顔がとても印象的でした。徳永さんは16歳で京都に来て、御召(※)専門の会社でお仕事をしながら、絣の勉強をしておられました。毎朝早くからの仕事に、3年目には辛くて辞めたくもなったそうですが、約10年の期間を経て独立を果たしました。昭和40年前後、西陣には絣加工業者は120軒以上あったのですが、今では7軒にまで減ってしまっています。しかし、徳永さんは今でも西陣で活躍されている方なのです。
 そんな徳永さんの愛する絣織の特徴と歴史を少しお話しましょう。絣織は、あらかじめ模様にしたがって染め分けた糸(絣糸)を用いて織り上げた織物です。私たちも目にしたことのある矢の羽模様の着物は絣織の代表的な模様です。絣の技法は手くくりと呼ばれ、糸の染めたくない部分に紙やゴムを巻いて糸を染める技法です。単純に並べると単なる縞模様ですが、これを微妙にずらしていくことによってこのような美しいたて絣のボカシが作られるのです。この作業には「はしご」という独特の装置を使います。30センチほどの幅に約4,000本の糸を25から100段程のはしご(西陣で考案された、糸をずらす道具)を人の手で通すことにより、染まった絣糸を少しずつずらして長い縦糸に高低差をつけることで美しい絣の模様が描き出されるのです。
そんな徳永さんの愛する絣織の特徴と歴史を少しお話しましょう。絣織は、あらかじめ模様にしたがって染め分けた糸(絣糸)を用いて織り上げた織物です。私たちも目にしたことのある矢の羽模様の着物は絣織の代表的な模様です。絣の技法は手くくりと呼ばれ、糸の染めたくない部分に紙やゴムを巻いて糸を染める技法です。単純に並べると単なる縞模様ですが、これを微妙にずらしていくことによってこのような美しいたて絣のボカシが作られるのです。この作業には「はしご」という独特の装置を使います。30センチほどの幅に約4,000本の糸を25から100段程のはしご(西陣で考案された、糸をずらす道具)を人の手で通すことにより、染まった絣糸を少しずつずらして長い縦糸に高低差をつけることで美しい絣の模様が描き出されるのです。
絣織の歴史は紀元前にさかのぼります。発祥の地はインド・ペルシャと考えられています。当時、身分の高い女性が矢絣模様の腰巻を使っていました。その後、中国を経て琉球に絣織の技術が伝わります。琉球では身分に関係なく多くの方に広まりました。琉球から薩摩に、ついには全国に広がりました。今では西陣織にも使われる伝統的な技法です。
 西陣織は何人もの方がひとつの織物を作るのに携わっています。徳永さんは、「自分が作った糸が次に織手さんに渡っていく。顔も名前も知らない方ですが、糸と同時に心遣いも届けることを忘れないようにしています。」と、おっしゃっていました。印象的であったのは、織手の方に渡す際に,少しでも糸に問題があれば何でも言ってほしいという事と電話番号を書いた手紙を同封するというお話でした。自分が作った糸に絶対的な責任を持つ徳永さんは一流の職人。厳しい世界の中で60年間続けてこられたのは徳永さんのこの職人魂なのだろうと強く思いました。
西陣織は何人もの方がひとつの織物を作るのに携わっています。徳永さんは、「自分が作った糸が次に織手さんに渡っていく。顔も名前も知らない方ですが、糸と同時に心遣いも届けることを忘れないようにしています。」と、おっしゃっていました。印象的であったのは、織手の方に渡す際に,少しでも糸に問題があれば何でも言ってほしいという事と電話番号を書いた手紙を同封するというお話でした。自分が作った糸に絶対的な責任を持つ徳永さんは一流の職人。厳しい世界の中で60年間続けてこられたのは徳永さんのこの職人魂なのだろうと強く思いました。
徳永さんは現在、女性のお弟子さんに絣織の技法を伝えています。お弟子さんとは、仕事だけでなく食事なども一緒にとりながら、たくさんのお話をしておられるそうです。
「弟子には絣織の技法だけでなく、仕事をするという心持ちと誇りも伝えたい。」
絣織の技法とともに徳永さんの職人魂も未来につながっていくのだと強く感じました。 (執筆者:片山菜穂)
※主として和服に用いられる絹織物の一種。
 絣織りの技術は継承され現存されているという伝統の大切さを実際に工房に訪れてひしひしと感じました。職人さんとお弟子さんのみならず、お手伝いさんや他の職人さんなどの多くの人の繋がりと技術によって,絣織は,今も継承されています。その行程には,今も昔と変わらない互いの伝統技術によって繋がれた縁の橋が架けられている…ということを感じざるを得ませんでした。貴重な道具を見せていただき、とても興味深かったです。(井上)
絣織りの技術は継承され現存されているという伝統の大切さを実際に工房に訪れてひしひしと感じました。職人さんとお弟子さんのみならず、お手伝いさんや他の職人さんなどの多くの人の繋がりと技術によって,絣織は,今も継承されています。その行程には,今も昔と変わらない互いの伝統技術によって繋がれた縁の橋が架けられている…ということを感じざるを得ませんでした。貴重な道具を見せていただき、とても興味深かったです。(井上)
絣織が、インドからはるばる伝わって来た歴史の奥深さが興味深かったです(3,000年近くも前からある織物だとは思っていませんでした)。お嫁さんに贈る矢絣に「お嫁に行ったまま(矢のように)帰って来ないでほしい」という思いが込められているユニークさには驚きました。(西田)