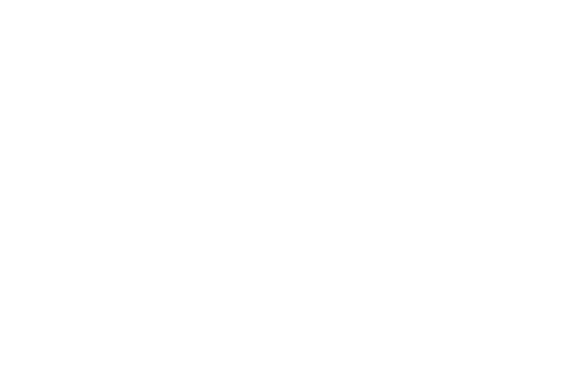2014年3月24日
~綴れ織りの技術と基本理念~
平野 喜久夫さん 【瑞宝単光章 伝統工芸士】
今回お話を伺ったのは、瑞宝単光章・伝統工芸士の平野喜久夫さんです。主に「綴れ織り」を生業とされています。
平野喜久夫さんは、約60年間「織物」の仕事に参与されています。「西陣織」の織り技法は12種類あります。主に「綴」(つづれ)「経錦」(たてにしき)「緯錦」(よこにしき)「緞子」(どんす)「朱珍」(しゅちん)「紹巴」(しょうは)「風通」(ふうつう)「捩り織」(もじりおり)「本しぼ織」「天鵞絨」(ビロード)「絣織」(かすりおり)「紬」(つむぎ)です。その一つの「綴」が今回の主題となる織物です。「綴」は能の衣装や帯などに留まらず、大きな額、掛け軸にも用いられています。
 「綴れ織り」には他の「西陣織」にはない幾つかの特徴があります。一つ目は,技術習得は,無地であれば半年くらいで織ることが可能となりますが,深めていくには本人の取り組む姿勢と分析力が必要と考えられます。二つ目は、ジャカード機(Jacquard)を使用しない事です。なぜならジャカード機は数えるほどの色彩しか表現できないからです。故に、「綴れ織り」はジャカード機を使わない事によって無限の色彩を顕わにできるのです。また縦糸が表出されません。(あえて出す事はある。)それゆえ精密な織物が創成されます。此処に「綴れ織り」の神髄があるのです。
「綴れ織り」には他の「西陣織」にはない幾つかの特徴があります。一つ目は,技術習得は,無地であれば半年くらいで織ることが可能となりますが,深めていくには本人の取り組む姿勢と分析力が必要と考えられます。二つ目は、ジャカード機(Jacquard)を使用しない事です。なぜならジャカード機は数えるほどの色彩しか表現できないからです。故に、「綴れ織り」はジャカード機を使わない事によって無限の色彩を顕わにできるのです。また縦糸が表出されません。(あえて出す事はある。)それゆえ精密な織物が創成されます。此処に「綴れ織り」の神髄があるのです。
平野さんは、経験によって蓄積された基本理念を持っておられます。それは「需要の創造と伝統的技術を残す」ことです。平野さんは真に価値ある物の創造を念頭に置かれています。けれども後継者が食べていくためには、ある程度消費者の需要に合わせていく必要性があるとも考えています。その為には、売れる物の創造と伝統的技術継承の両輪を廻さねばなりません。しかしその道の先には真に価値ある物を生成するといった確固たる目的があるのです。
日本各地からは定期的に「綴れ織り」を習いに来る後継者の方々がいます。遠方では、埼玉から夜行バスで来る方もいます。現在は、後継者の多くの方々が本業を持っていますが、ゆくゆくの目標は「綴れ織り」で生計を立てていくことにあります。その為には、「需要の創造と技術を残す」事が要になってきます。複雑怪奇な「綴」という代物と対自することによって、製作技術だけではなく、仕事の幅を敷衍(ふえん)していくプロデュース能力が求められているのです。
職人業界に生じている幾つかの問題点も挙げられていました。他の業界でも起こっている事だと思われますが、多くの業界人が抱く画一的様式が職人の世界をも覆っているとのことです。ゆえに固定思考から柔軟思考へ、小業界から小業界間の連携の重要性を指摘されていました。また消費者の動向ばかりに焦点を合わせすぎることへの危険性を指摘されていました。伝統的技術と市場的需要を両天秤に掛けながら支えてゆく姿勢から真剣さと侘しさが犇々(ひしひし)と伝わってきました。
「伝統」と「モダン」の話では、双方の融合を指摘されていました。双方とも今まで積極的に関与をしてこなかった為にどのように関与していいのかが不明瞭なのだと指摘されていました。今後の「伝統産業」、「革新産業」の課題の一つであると思われます。LEDを使ったイルミネーションを見せて戴きました。現代的な色彩の中に伝統的な「綴」が顕証(けんしょう)されていました。
全体を通じて、殊更印象的だったのは、平野さんの「技術は見て覚えるのは間違いである。」というご指摘でした。技術には「見て覚えられるもの」と「見て覚えられないもの」があります。私は技術とはその隙間に潜む物だと考えています。技術とは植物の蔓(つる)のように、様々な性質が交錯し合う事によって創成されるのです。
最後に平野さんから「若者へのアドバイス」を戴きました。それは「人がやっていることをちゃんと見なくてはならない。」という言葉でした。人は情識(じょうしき)という殻に閉じ篭りやすく、安い安寧を得たいものです。この言葉は、「たえず他人の動向を観察して、たえず創造していく」平野さんの人生を表していると思います。他者から学ぶ余地は如何なる時代においても、如何なる年代においても、如何なる立場においても、幾らでも残されているのです。(執筆者:達城 直洋)

○感想○
・時間をかけて細かい部分までこだわったものを作りたいという理想と、需要のあるものを作らなければ産業として成り立たないという厳しい現実が伝わってきました。人より良い織物を織ることが職人の誇りだとおっしゃっていたのがとても心に残っています。(西田)
・綴れ織りの伝統を後世に残していこうとする平野さんの強い想いをお話を伺うなかで感じました。平野さんご自身がこれまで培ってきた技術を、古き良き伝統を中核に据えながら、現代に合うような作品や思考のスタイルを考えている点に平野さんの柔軟性や綴れ織りが持つ魅力を感じました。(日裏)