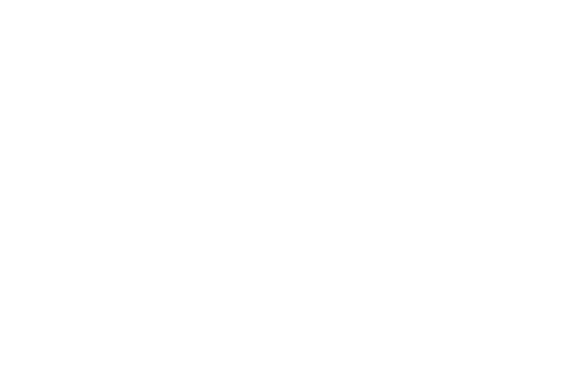2013年11月26日
町家を通して歴史と文化を伝える
古武博司さん 【「西陣の町家・古武」主宰】
 |
今出川通りと大宮通りが交差する道を少し北へ上がったところに、趣あるたたずまいの「西陣の町家・古武」はあります。現在ここは、JICA(国際協力事業団)や企業・団体等の研修、コンサートや展示会など様々な文化的活動が開催され、人々の交流の場となっています。今回は、この町家を通して京都西陣の歴史や文化を伝え、地域を盛り上げるための様々な活動をされている古武さんにお話を伺いました。
古武さんが現在の活動をはじめるきっかけとなったのは、16年前(1988年)に不動産業を営む友人に案内されてこの町家を訪れたことです。職住一体である町家は地場産業が弱まったことで不要となり、昔ながらの町家を壊して集合住宅にしようという動きが活発になっていました。案内された町家も集合住宅となる計画があり、取り壊される予定になっていました。しかし、大正時代に建てられたこの町家は、元禄時代に完成した町家の原型を当時に再現したものとわかり、地域の歴史や文化を伝えているこの町家を残したいと思い、所有権を取得することになったそうです。そしてその目的を果たすために、「地域の集会所や文化的な催し物会場として利用をしながら、保存することができれば」と考えたことから、文化的催し施設としての「西陣の町家・古武」の活動が始まりました。この古武さんの活動は、町家の価値を見直す国や京都市の動きとちょうど一致し、活動の場を広げていきました。
現在、古武さんは、町家を会場として各種団体・個人の研修や大学などでのゲストスピーカーとしての講義活動や、地域の歴史と文化を語ることでその地域の魅力を引き出し、観光にお越しになる方々により楽しんでもらおうという「語り部観光」といった活動をされています。観光面では、西陣地域における1200年間に及ぶ為政者の営みと織り産業を重層的に捉えて西陣の町全体をミュージアム化し、街の活性化を図ってゆこうとする「西陣・町ミュージアム構想」検討委員会の事務局活動もされています。この構想は、上七軒・大黒町・小川通りを石畳にしてその石畳ラインを結んで歩くと、年間70万人が訪れる観光スポットとなっている西陣織会館にも立ち寄って、西陣地域をぐるっと観光ができるようにするという、行政とも連携した大規模な構想です。
地域の歴史を伝えるという面では、1945年6月26日の西陣地域の空襲被害地域を訪ねる活動をされています。この空襲被害は、京都市民にもあまり知られていないそうです。また、戦没者を悼み平和を願って鐘をつく「平和の鐘をつく会」にも携わっています。

様々な活動をされている古武さんですが、全ての活動のベースは「町家を残したい」という思いです。西陣地域は、平安時代に天皇・公家・貴族・僧侶等が着用する装束を織る工人(こうじん)が集まって成り立ちました。後年、自宅住居で織物生産もしたことで、人々の生活は産業と密接に結びついていきました。産業と密接に関連した生活スタイルの中から生まれた町家を残すためには、地場産業を盛り上げることが大切、との思いから「西陣・町ミュージアム構想」にも関わるようになったということです。
町家の歴史と文化はその外見だけではなく、うなぎの寝床と呼ばれる間口が狭く奥行きの深い構造と各部屋のしつらえ、そして畳や欄間(らんま)・ふすまなどその内装にあると古武さんは話されます。
しかし、これらの物を作るための国産材料は減少し、技術の継承も難しくなってきています。また、町家が新たに作られなくなったため、今では町家の構造を知る大工さんが非常に少なくなり、この町家を壊してしまうと復元することが難しいというお話をうかがい、今まで漠然としか感じていなかった町家の貴重さを再認識しました。
東日本大震災以降、「日本の文化・物作り、自然との調和が大切」という視点で町家を訪れる人が増えたそうです。京都が都となってから1200年間、天変地異を乗り越えてくることができたのは、ライフラインが自然に寄り添っていたからと古武さんは話されます。このような認識を持つようになった人が増えてきた中で、日本の伝統の町家はますますその価値を見直されていくのではないかと感じました。(執筆:荒木柚乃)
〈町家とは〉
工場(こうば)や店舗と一体となった住居です。商業が活発化した江戸時代の元禄期(1688~1704)にその様式が完成しました。一般的なものは間口が狭く奥行きが深いため、「うなぎの寝床」と呼ばれます。間口が広いほど多くの税金が課されたため、このような構造が生まれました。しかし、祇園祭の山鉾が建てられる四条室町や新町界隈には、深い奥行きとともに間口も広い商家が数多くあります。近年、その良さが見直されて保存・再利用がされるようになっているものの、住人の高齢化や建て替えの困難さから、その数は徐々に減ってきています。
「西陣の町家・古武」
住所:〒602-8438 京都市上京区大宮通五辻上ル
TEL:075-441-9620
○感想○
・町屋を残す、という目的からこれほど幅広い活動をされていることに驚きました。特に、「西陣・町ミュージアム構想」のお話が興味深かったです。課題も多いですが、うまく形になってほしいと思います。
インタビューの最後に、これからは経済的な格差が広がり家族を養うのも大変だが若い人たちが頑張っていってほしい、というお言葉を頂けて心強かったです。 (西田)
・本文には書くことができなかったのですが、古武さんお手製の町家の模型を見せてもらいながらの伝統的な町家から商店街の商店へと時代とともに姿を変えてきた町家の説明が、分かりやすくおもしろかったです。「町家を残したい」という一つの思いを様々な活動に発展させていることからもうかがえるように、古武さんはとても好奇心旺盛な方で、精力的に活動されている姿がとても印象的でした。(荒木)