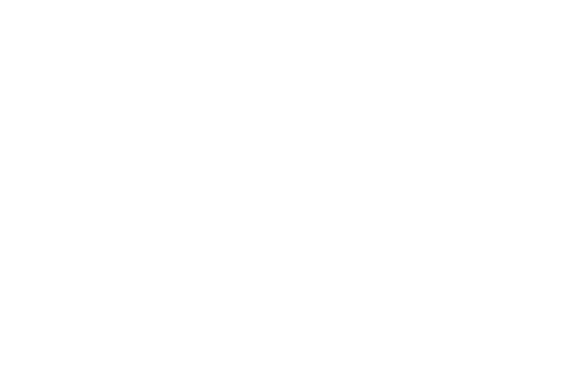2013年10月18日
手織りを大切に~
津田 功さん 【伝統工芸士】
 |
今回お話を伺ったのは、伝統工芸士の津田 功さん。現在、渡文株式会社の工場長をされています。
愛媛県で育ち、高校を卒業すると同時に親戚の紹介で西陣に来られ、この道46年のベテランです。
津田さんの案内で見学させていただいた工場では現在7名ほどの職人さんが勤務されています。平成2年当時では職人さんは、400名ほど勤務されていたようで、およそ20年の間に職人さんの数が大幅に減少してしまいました。現在最年少の織り手さんは25才だそうです。
津田さんは、帯の手織りをされており、1つの帯を仕上げるのにおよそ1か月かかるそうです。1日に織れる長さはおよそ15センチほどだそうです。今回見させていただいた織物は経糸が4,800本あり、横糸1センチ幅を織るのに32回織らなければなりませんでした。経糸が1本でも切れたらその時点で売り物にはならず、経糸が長いほど糸がしなやかに均等にのびるそうです。反対に機械は経糸が短いために完成した反物は重くなってしまうそうです。織物を作るには、図案を企画し作成する人・綜絖する人・糸を整える人・染色する人・金箔を貼る人・織る人の少なくとも6名の方が関わります。そして、津田さんはこのリレーのアンカーを務めているのです。
津田さんが話された「織物は誰でもできるんです。織物は織れても、売り物は織れない。これにはプロの技が必要なんです。」というこの言葉が印象深く残っています。

また、糸の基となる「つむぎ」と「生糸」のちがいを詳しく説明してくださいました。「つむぎ」とは簡単に真綿からつむいだ糸のことで、「生糸」は7個の繭からできているそうです。繭選びにも良し悪しがあり、繭がくびれているものが良い繭だそうです。糸は、ほとんど海外で生産されていて、ブラジルから輸入しており、日本には大きな製糸工場は3軒しかないのが現状です。
この西陣のまちが、なぜ今まで織物産業都市として栄えてきたのかは、「湿度・水が織物に適しているから」と津田さんおっしゃっていました。多くの職人さんによって伝統産業リレーが行われ、誰もがこのまち、製品において欠かせない重要な人たちであり、これを守っていかなければならないと強く思いました。(執筆者:山中美穂)
*その他のスタッフの感想*
・・手織りの帯をさわらせてもらい、その軽さ・しなやかさに驚き、手織りと機械織りのちがいを初めて知りました。また、織物は能や日常で使う言葉といった、様々な文化に影響を与えていることも知りました。技術面から考えても文化面から考えても、手織りがずっと伝えられていってほしいと思いました。(荒木)
・津田さんが、「帯を織っているときはお昼休みのベルの音も聞こえない」とおっしゃっていたのが、印象的です。職人のプロの技と、貴重なお話をたくさん聞くことができ、大変有意義な時間でした。(今井)
・ご自身の職業に誇りと愛情を持っているからこそ、妥協を許さず、素晴らしい作品を作り続けていくことができるのだと感じました。津田さんの機織りの技術が将来へと続いていってほしいと思いました。(日裏)