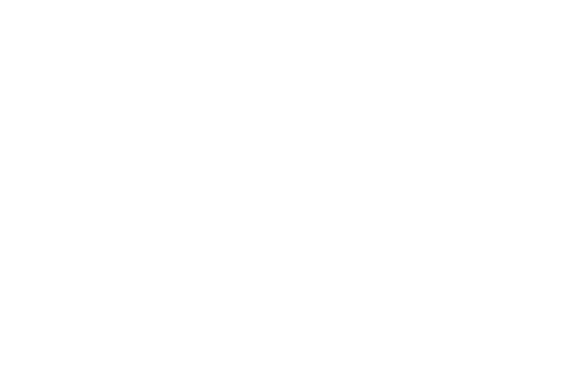「人と仏教をつなぐ浄福寺」
【浄福寺 住職 菅原好規さん】
 |
今回は、前回インタビューをさせていただいた大久保さんが勤めている蜂蜜店「ドラート」で偶然お会いすることができた、浄福寺の住職をしておられる菅原好規さんにインタビューを受けていただきました。
浄福寺通りを歩いていると突然現れる赤い門。これが浄福寺の門です。中に入ると、左手には浄福寺幼稚園があり、まっすぐ進んだ先に「日本最古の違法建築」といわれる浄福寺の本堂があります。赤い門はとても印象強く、赤門寺とも言われているのですが、浄福寺には門は2つあります。上の写真の赤い門と、本堂の向こう側にある黒い門です。敷地に対して斜めに2つの門を構えているので、地域の人は近道するための通り道として使われることも少なくないそうです。
浄福寺は延暦年間(782~802年)に天台宗の寺として建立され、当時は京都二十五大寺の一つに数えられていました。室町時代末期の大永5年(1525年)に後柏原天皇から念仏三昧堂の勅号を賜って浄土宗を兼ねるようになり、その後何度か移転をし、元和元年(1615年)に現在の場所に定まりました。
このお寺の周辺について伺ったところ、昔は西陣織の織物屋からカタカタという音がよく聞こえていたそうです。特に賑わいをみせていたのが、地蔵盆の時。今の笹屋町通りの浄福寺通から千本通りまでの間、たくさんの織物屋が、各店でその年の流行などを織物にして表現し、展示していました。当時ではまだ珍しいと思われる外国人も世界中からきていたそうで、今と変わらない道幅にたくさんの人が集まっていたというから驚きです。
そんな素敵な場所にある浄福寺で、7年前に住職になられた菅原さんは、一般の人たちにも浄福寺のことや仏教のことをもっと知ってもらいたいという思いから、様々な工夫をされてきました。
例えば、未公開品の特別公開がされた時は、展示物や、建築手法についてを固く説明するよりも、学園祭の展示のようなものがしたいと考えられました。その結果、仏教のことを紙芝居風に説明できる絵解き、若者にも関心をもってもらえるよう学生ボランティアによる絵解きもされました。他にも木版画や、仏教用語をわかりやすく理解できる手作りの双六など、楽しく仏教を学んでもらえるようなものにしたかったという思いで行ったもののウケがよかったそうです。
他にも、情報発信の役割をするために本堂の横に掲示板を設置しました。その掲示板を見ると「Twitterはじめました」と書いてあります。3か月ほど前から始
められたTwitterでは浄福寺を知らない人にまで情報が広まります。Twitterの140字に写真1枚というスタイルは、数枚の絵を少しずつ説明していけるので、菅原さんがされている絵解きと合うのだそうです。「Twitterでも身近な人を大事にしていると、どんどんそこから輪が広がっていくところが凄いんです!」とおっしゃられています。
こうした工夫をしていくようになって、少しずつ浄福寺を訪れる人が増えていったといいます。
最後に、今の若者に伝えたいことについて伺いました。
「今の子どもたちは、何でもできるところが凄い。趣味が2つも3つもあったり、特技があるのはとても良いことだと思う。でも、本を読むということも大事にしてほしい」とのこと。
 |
昔は、本がとても高価なものでした。二宮金次郎の伝記では、彼は本を盗み読んでいたといいます。本屋で読んでは内容を覚えて家に帰り、紙に書き写していたということです。菅原さん自身も、学生のころは本屋に通って何百冊も読まれていました。昔は本を読むことが勉強だったといいます。「本を読むことは、読解力がつくということだけではない。すぐには身につかなくても、大人になると不思議なもので、勉強してきた色んなことが一つにつながる。その積み重ねてきた勉強の差は明確になってくる」
また、「自分の好きなことをしていると、いつか成功する」ということもおっしゃっていました。一度仕事に就いて、今一つだなぁと思いながらずっと仕事をしている人はなかなか芽がでないことが多いけども、夢を追い続けて努力をした人は本当に芽がでるのだそうです。「今は就職も難しいかもしれないけど、妥協はするべきではない。仕事をとにかく見つけ、落ち着いたら、好きなことに近づけるようにしていくと良い人生になるだろう。人は何度でも変わるチャンスはあるのだから」
お話しをしてくださっている菅原さんの表情をみていると、今自分がしていることの一つ一つは本当に大人になってもつながっていくのだろうなぁと感じることができました。
現在、浄福寺の釈迦堂は工事中になっていますが、工事が終わると「西陣釈迦堂」という名に変わります。この名は菅原さんが一人で考えたのではなく、地域の人たちにも意見を聞いて決めたそうです。そんな地域の人々に愛されている浄福寺ですが、菅原さんの新しいアイデアが加わり、これからもっともっとたくさんの人に愛されていくのだろうと思いました。
(執筆者:細田祥子)
☆他のスタッフの感想
・これまでお寺の住職の方と話す機会などなく、初めての経験で新鮮でした。特に、仏教用語の双六を作製したり、Twitterでの情報発信など、あらゆる人が仏教に親しみを持てるように創意工夫をしたりしているところが印象的でした。(浜田悠)
・Twitterや絵解きなど、想像していた以上に様々な取組みをされていて、お話を聞いていて楽しかったです。実際に双六をやらせていただいたり、屏風絵を見ながらお話を聞いたりして、仏教や説話に興味がわきました。(早川みなみ)
☆浄福寺へのアクセス、ご連絡はこちら ☆
京都府京都市上京区浄福寺一条上ル笹屋町 2-601
TEL:075-441-0058