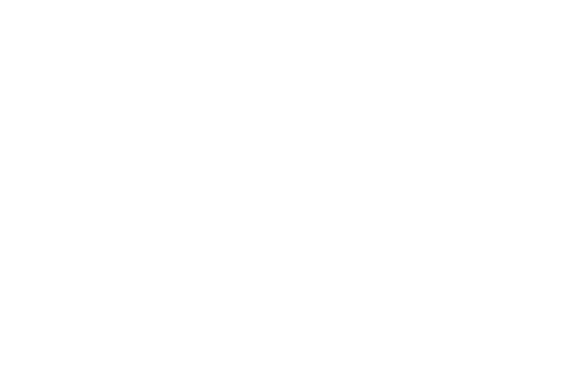「日本に暮らして」
【ジュディース・クランシー さん】
今回お話を伺ったのは、日本の建築や文化などを外国に紹介する本を書かれている、アメリカ出身の作家ジュディース・クランシーさんです。120年前の元織屋であるご自宅には、ご自身で生けた生け花や絵が飾ってありました。
 クランシーさんが日本に来たのは今から40年前になります。最初は韓国で平和活動のボランティアをしていたのですが、京都に住みたいと思っていたこともあり来日されました。元々のきっかけは、10歳のとき、ア ジアに行っていた同級生からおみやげをもらい、お箸を使う、家の中では靴をぬぐという習慣を聞かされ、また雑誌で日本の文化を知り、興味を持ったことでし た。日本に来た当時、日本語の勉強をするにも辞典がなくて、最初のころは苦労したとおっしゃいました。大阪でカネボウに勤め、国際室長付で手紙の用意や通 訳など、秘書のような仕事を経験してきましたが、やめました。その後は、関西大学や大谷大学で外国語の講師をしています。現在、西陣に住んでおられます が、住み始めようとしたときは、西陣は閉じている社会という印象があり、住民に受け入れてもらえるか不安に思っていたといいます。西陣に住んでいる人は近 所の人をみんな知っていますし、元は古い織屋という家が多く結びつきが強いからです。ただ、近所の方と実際話してみて、このくらいの日本語なら大丈夫だと 聞いて、受け入れてもらえたので住むことにしました。
クランシーさんが日本に来たのは今から40年前になります。最初は韓国で平和活動のボランティアをしていたのですが、京都に住みたいと思っていたこともあり来日されました。元々のきっかけは、10歳のとき、ア ジアに行っていた同級生からおみやげをもらい、お箸を使う、家の中では靴をぬぐという習慣を聞かされ、また雑誌で日本の文化を知り、興味を持ったことでし た。日本に来た当時、日本語の勉強をするにも辞典がなくて、最初のころは苦労したとおっしゃいました。大阪でカネボウに勤め、国際室長付で手紙の用意や通 訳など、秘書のような仕事を経験してきましたが、やめました。その後は、関西大学や大谷大学で外国語の講師をしています。現在、西陣に住んでおられます が、住み始めようとしたときは、西陣は閉じている社会という印象があり、住民に受け入れてもらえるか不安に思っていたといいます。西陣に住んでいる人は近 所の人をみんな知っていますし、元は古い織屋という家が多く結びつきが強いからです。ただ、近所の方と実際話してみて、このくらいの日本語なら大丈夫だと 聞いて、受け入れてもらえたので住むことにしました。
 作家としての仕事は、25年前、小原流のお花の先生に話を聞いたことがきっかけでした。その先生は買った花ではなく、山で直接とってきた花を使っていました。日本の美術、幽玄、雅の説明を受け、生け花の本を執筆しました。その後、アメリカで「exploring Kyoto」という本を出版しました。「exploring Kyoto」では、日本に来る外国人観光客向けに、宗教、遊び場、スーパー銭湯の入り方などを紹介しています。「京都」というと、私たちは日本の観光地の定番と感じますが、実際には京都についての外国人観光客向けの情報はほとんどないという問題があったのです。取材では京都の名所を30ケ所回り、お 寺に行ってチラシをもらったり、看板を翻訳します。比叡山については山の地図も書き、道の名前の由来についても書かれています。外国人としては、各観光地 での詳しい歴史や年号(例えば、豊臣秀吉が何年から何年まで生きた)といった情報にはあまり関心がなく、どんな風に建築したのか?神道はどんなものか?ど うして神社は作られたのか?神社とお寺の違いは?といった単純な疑問の方が知りたいといいます。また最近では「machiya gohan」(まちやごはん)という本を作っています。140軒のレストランを自ら食べまわり、料理やサービス・建物をじっくり検討して書き上げられるそうです。
作家としての仕事は、25年前、小原流のお花の先生に話を聞いたことがきっかけでした。その先生は買った花ではなく、山で直接とってきた花を使っていました。日本の美術、幽玄、雅の説明を受け、生け花の本を執筆しました。その後、アメリカで「exploring Kyoto」という本を出版しました。「exploring Kyoto」では、日本に来る外国人観光客向けに、宗教、遊び場、スーパー銭湯の入り方などを紹介しています。「京都」というと、私たちは日本の観光地の定番と感じますが、実際には京都についての外国人観光客向けの情報はほとんどないという問題があったのです。取材では京都の名所を30ケ所回り、お 寺に行ってチラシをもらったり、看板を翻訳します。比叡山については山の地図も書き、道の名前の由来についても書かれています。外国人としては、各観光地 での詳しい歴史や年号(例えば、豊臣秀吉が何年から何年まで生きた)といった情報にはあまり関心がなく、どんな風に建築したのか?神道はどんなものか?ど うして神社は作られたのか?神社とお寺の違いは?といった単純な疑問の方が知りたいといいます。また最近では「machiya gohan」(まちやごはん)という本を作っています。140軒のレストランを自ら食べまわり、料理やサービス・建物をじっくり検討して書き上げられるそうです。
「外国人の日本に対する印象はあまりいいものではない」とクランシーさんはおっしゃいます。モノの値段が高いで すし言葉も通じない。そして、情報があまりないからです。日本についての本はありますが、「日本といっても東京の本がすごく多い、京都の方が面白いのに」 と残念そうでした。
京都では、鴨川や御所、堀川のイチョウ並木が好きだといいます。お花のけいこも長く続けられており、日本の暮ら しや文化を積極的に楽しんで生活されていると感じました。「日本人は日本のことを知らない。オックスフォードでは、そこの住民は街の名所について説明でき ます。京都の人は京都の名所を説明できません。歌舞伎を鑑賞したこともない人が多く、日本独自の文化に興味がない。大学で学生に木の葉を見せて、英語を教 えようとしたとき、楓は分かってもらえましたが、日本人に馴染みの深い桜の葉を「杉」と答えられてがっかりしたこともありました。若い人には色んなことに 興味を持って欲しいとクランシーさんはおっしゃいます。旅行に行くのも、新しい習い事をするのもいいと思う。ただ、旅行に行くなら旅先の社会に飛び込ん で、人と話して、ちゃんと記憶して帰ってきて欲しい。そういうことを通じて、自分の目が覚めるような体験を味わってほしいし、自分の文化の何が好きで嫌い か話せるようでいてほしいと話されました。
(執筆者:近藤貴弘)
☆他のスタッフの感想☆
・外国の方の日本に対する印象や、観光地といえば京都と思っていたのに、まだまだ情報が少ない点など、自分が思っていたものと大分違うのが直接お話しさせて頂いて分かりました。仕事・習い事・遊びなどを通じて、日本文化の色々なことに興味を持って、実際に体験して楽しんでいる姿が印象的でした。(山田)
・外国の方から見た日本、日本人についてのお話を伺うことができたのが面白かったです。自国についてもっと関心を持ち知ろうと思いました。(早川)