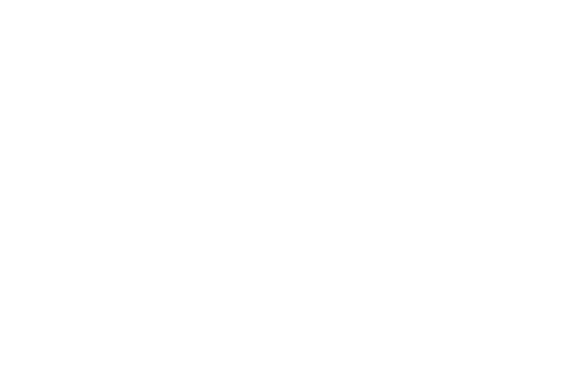「子ども〜いま、むかし〜」
学童保育指導員 龍野麗子さん
今回は、京都市内で学童保育をされている龍野麗子さんのお宅に伺いました。
龍野さんの生まれは福岡県の大牟田、炭坑の町です。27才のときに京都に移り、始めは北白川の近くに住んでいましたが、町家に住みたいなと常々思っていたこともあり、西陣の現在のお家に落ち着きました。龍野さんが学童保育の仕事を始めたのは30年ほど前になります。学童保育の仕事では、編みものをしながら片手間で子どもの面倒をみる、といった皮肉を込めて「編みものおばさん」と呼ばれていた時代もあったそうです。専門的な仕事として扱ってもらえないこともあり、就労条件も良いとは言えないのが正直な所だと言います。しかしそれに対して仕事の内容はとても楽しいと龍野さんは感じています。現在は東山区内の学童保育所に所属していますが、その他の場所でも指導員を経験されてきて、様々な子どもを見てこられました。学童の放課後の安全や健やかな育成、日常生活の安定、保護者の就労支援等を目的に、日々放課後から夕方のあいだ、子ども達の見守りや生活の指導、おやつの提供や季節ごとの行事を計画し、子ども達が学童保育所で充実した時間を過ごせるように、子ども達の意欲を形にするイベントを行っています。長年、学童保育に関わっていると子どもの生活の移り変わりが見えてきます。「とにかく今は子ども達が忙しすぎますね。昔に比べれば授業時間が延びたし、塾や習い事をする子が多く、疲れているけど、素直にこなすんですよ」することが多い中で、ほっこりできているのかなと考えます。目一杯遊ぶ時間は少なくなりました。遊び方も昔はよく外を駆け回っていましたが、ゲームやテレビを使うように変化しました。頭に入ってくる情報の多い時代の中で、知っているが体験していない、本当の意味で分かってはいないことが増えているのかもしれません。また、小学校の統合で登下校に時間がかかる所もあります。広い地域の子どもが集まることで「地元」という感覚がつくりにくくもなってきていたり、同級生とは仲良しでも自然と下級生の面倒を見るといったりしたことは減りつつある様です。自分の世界を大切にする傾向があって、人の話が聞けないことや、自分が集中している事とやらなければいけない事との切り替えができにくい傾向も見受けられます。かといって強く自分のしたいことを言葉で主張するわけでもないと云います。子どもにとっての時間やその使い方、遊び、人間関係は複雑になっているのだなと感じます。仕事のやりがいについて尋ねると、「やっぱり子どもの成長ですよ」とおっしゃいます。「出来なかったことが、この1年でもうこんなに出来るようになったんやと喜びを感じたり、友達の前で振る舞っているのとは違う、その子の本当の素直な面とか優しさもろさ、色んな表情を見たりすることができます」
かつて長屋であった古めかしいご自宅は元織屋です。お隣からは機織りの音が聞こえる日もあり、近隣も元織屋や織り機の修理屋など西陣織関連のお仕事をされていました。「機織りしいや。お給料1日で稼げるで」と言われたことがあるほど、羽振りのよかった時代もありました。これまでのインタビューでもお聞きしてきましたが、改めて西陣が織物の町として栄えていたことと、そこに関わる人の多さを伺い知ることができました。「今は庶民が日常生活で着物は着ないから。イスを使う生活だし、畳も減ったしねえ。すごい特殊な能力や技術の織り仕事だけが生き残っているかんじ」そんな印象があるようです。近くに住む人は高齢の方が多く、若者はカフェ「さらさ西陣」によくいます。町内にも若者が定住すればいいと感じておられますが、結束が固い土地なので入りにくさはあるかもしれません。しかし馴染むのに時間がかかっても、皆穏やかでよい場所です。
地域のおすすめスポットは大徳寺高桐院だと教えて下さいました。秋の静かな朝の紅葉は、地面に落ちたもみじと木の上のもみじのコントラスト、そして光のあたり具合が最高に美しいのです。
(執筆者:山田絵理香)
☆他のスタッフの感想
・学童保育自体を私はあまり知らなかったのですが、子ども達の将来のことを真剣に考えて接している龍野さんの話を聞き、よく観察して、よく考えることが社会人として必要だと実感しました。(近藤貴弘)