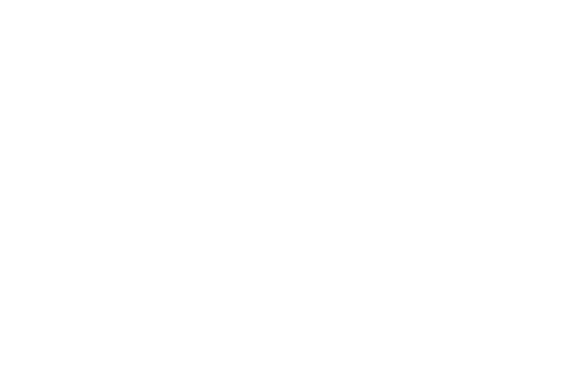当センターでは、演劇やダンス初心者を対象に、
舞台公演づくりという共通の目標を成し遂げる活動で
グループ体験の機会提供を行ない、青少年の自分づくりを支援しています。
その1つ、創作ダンス事業の始まりは、1994(平成6)年の中京青年の家(現中京青少年活動センター)。
モダンダンスワークショップという事業名でスタートしました。
これは、コンテンポラリーダンサーの砂連尾理さんと寺田美砂子さんを講師に迎え、
半年間をかけて創作ダンスの自主公演づくりを目指すというものでした。
当時、ワークショップということば自体もあまり世の中には浸透していなく、
コンテンポラリーダンスと聞いて、すぐにわかる人も少なかった。
3年目からは事業名をDance Performance Workと改め、プログラム内容も少し整理をして、
その後、少しずつ改良を加えながら、2004年(平成16)まで11年間実施しました。
2005(平成17)年からは、その後継事業として、同じくコンテンポラリーダンサーの
佐藤健大郎さんと大槻弥生さん(2008年まで)をナビゲーターに迎え、
ココロからだンスW.Sを実施しています。
修了公演の前には、近隣の学校を訪問して児童・生徒とダンスで交流し、
創作途中の作品の中間発表もしています。



参加者のニーズは踊りたいということにとどまらず、もっと広い意味で体を動かしたい、
体のことも含め、自分自身のことをもっと知りたい、あるいは変えたい、ストレスを発散したい、
何か打ち込むものがほしい、公演づくりによって日々の充実感や、
やり遂げる達成感を感じたいなど様々で、ダンス以外の期待も知ることができます。
創作ダンスの作品づくりの特徴は、なかなか思うように動かない
自分の体を意識することから始まります。
自分の体と向き合う作業は4か月間にも及びますが、
その作業は、自分の体についての記憶も一緒に呼び覚まし、
同時に、それに付随する感情なども思い出され、ダンス創作をしながら、
自分自身の内面的な出来事の整理も同時にしなければならないという場面も生まれます。



公演終了後のふりかえりでよく語られるのは、自分の体に対する発見です。
箸の持ち方や歩き方のくせに始まり、筋肉の使い方のくせなど、
自分の日常的な動作が意識化されることで、
それが自分の体に対する見方にも変化をもたらします。
そうした変化は、自分の体だけでなく、人や物との関わり方、認識が変化し、
さらには大きなライフスタイルの変化にもつながっていきます。
次は受容性です。自分と向き合って搾り出すようにして出てきた動きが、
その人らしいダンスとして尊重される、その人のコンプレックスも含めて、
その人らしさがそのままダンスになっている、という見方が創作ダンスの大きな特徴で、
素に近い自分が受容されたという体験が得られるのです。
3つ目は、価値観の幅が広がったということです。
受容的な雰囲気によって他の参加者との交流が進み、
その中でお互いの価値観を認め合うことで、自分の価値観も少し揺さぶられた結果です。
以上のようないくつかの変化は自分づくりの大きなヒントとなり、
事業終了後も参加者それぞれの次の生活場面に生かされています。